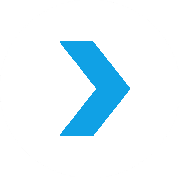キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
長谷部誠を思わせる遠藤航が見せつけた分析力と対応力、日本代表の欠かせない軸に/日本代表コラム
2020.11.14 15:00 Sat

2カ月連続でのヨーロッパ組のみでの欧州遠征。11月シリーズの初戦となったパナマ代表戦は、1-0で勝利を収めた。約1年ぶりの活動となった10月ではアフリカ勢のカメルーン代表、コートジボワール代表を相手に2試合とも無失点。結果は1勝1分けで終えていたが、パナマ戦に勝利し2連勝となった。
2年前に対戦した時とは監督もメンバーも変わっているパナマ代表。日本はキックオフから良い入りを見せたが、徐々にパナマが日本のプレスに慣れると、日本は押し込まれていないながらも窮屈な戦いを強いられた。その中で目立ったのが、後半から入ったMF遠藤航(シュツットガルト)だった。
◆南野のPKで勝利!日本代表vsパナマ代表 ハイライト
2年前に対戦した時とは監督もメンバーも変わっているパナマ代表。日本はキックオフから良い入りを見せたが、徐々にパナマが日本のプレスに慣れると、日本は押し込まれていないながらも窮屈な戦いを強いられた。その中で目立ったのが、後半から入ったMF遠藤航(シュツットガルト)だった。
遠藤航の関連記事
 キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
 ガーナ代表との一戦で、ピッチを支配したのはMF佐野海舟だった。MF南野拓実の先制ゴールを導いたボール奪取とラストパス。MF久保建英が真っ先に駆け寄ったのは、決めた南野ではなく、その起点となった背番号21のもとだった。日本代表復帰から約半年。彼はいま、ボランチ争いで一歩抜け出そうとしている。
■奪って、前へ。南野の
2025.11.15 13:30 Sat
ガーナ代表との一戦で、ピッチを支配したのはMF佐野海舟だった。MF南野拓実の先制ゴールを導いたボール奪取とラストパス。MF久保建英が真っ先に駆け寄ったのは、決めた南野ではなく、その起点となった背番号21のもとだった。日本代表復帰から約半年。彼はいま、ボランチ争いで一歩抜け出そうとしている。
■奪って、前へ。南野の
2025.11.15 13:30 Sat
 10月14日、東京スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ。
日本代表がブラジル代表を相手に、0-2から驚異の逆転劇を演じた。
14試合目にして初の対ブラジル勝利――。
世界が驚き、日本中が沸いた夜を、現地で取材した北健一郎と難波拓未が振り返る。
■歴史的勝利の価値
北:“サッカー王国”ブラジルを相
2025.10.16 21:00 Thu
10月14日、東京スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ。
日本代表がブラジル代表を相手に、0-2から驚異の逆転劇を演じた。
14試合目にして初の対ブラジル勝利――。
世界が驚き、日本中が沸いた夜を、現地で取材した北健一郎と難波拓未が振り返る。
■歴史的勝利の価値
北:“サッカー王国”ブラジルを相
2025.10.16 21:00 Thu
 【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表(日本時間9月7日/オークランド・コロシアム)
日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦。完全アウェイの野球場で勇敢に戦ったが、勝利とはならなかった。
アメリカ遠征を行っている日本代表は、7日にメキシコ代表と戦い、中2日の10日にアメリカ代表と対戦する。
2025.09.07 13:10 Sun
【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表(日本時間9月7日/オークランド・コロシアム)
日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦。完全アウェイの野球場で勇敢に戦ったが、勝利とはならなかった。
アメリカ遠征を行っている日本代表は、7日にメキシコ代表と戦い、中2日の10日にアメリカ代表と対戦する。
2025.09.07 13:10 Sun
 リヴァプールの日本代表MF遠藤航が、プレミアリーグ開幕節のボーンマス戦に途中出場。ダメ押しゴールをアシストするなどチームの勝利に貢献した。初戦からの活躍ぶりにファンたちが歓喜した。なお遠藤はこの試合でプレミアリーグ通算50試合出場を達成している。
昨季のプレミアリーグ王者であるリヴァプールは、開幕節でボー
2025.08.16 10:44 Sat
リヴァプールの日本代表MF遠藤航が、プレミアリーグ開幕節のボーンマス戦に途中出場。ダメ押しゴールをアシストするなどチームの勝利に貢献した。初戦からの活躍ぶりにファンたちが歓喜した。なお遠藤はこの試合でプレミアリーグ通算50試合出場を達成している。
昨季のプレミアリーグ王者であるリヴァプールは、開幕節でボー
2025.08.16 10:44 Sat
日本の関連記事
 東京ヴェルディとの試合を行うために来日したレアル・ソシエダ。28日には試合前日のトレーニングを行った。
25日にラ・リーガ最終節を戦い、27日に来日。ハードなスケジュールの中での来日となったが、選手たちはリラックスムードでトレーニングに臨んだ。
トレーニング前にはメディアの取材にイマノル・アルグアシル監督、
2024.05.28 23:15 Tue
東京ヴェルディとの試合を行うために来日したレアル・ソシエダ。28日には試合前日のトレーニングを行った。
25日にラ・リーガ最終節を戦い、27日に来日。ハードなスケジュールの中での来日となったが、選手たちはリラックスムードでトレーニングに臨んだ。
トレーニング前にはメディアの取材にイマノル・アルグアシル監督、
2024.05.28 23:15 Tue
 26日、高円宮記念JFA夢フィールドにて「JFA×KIRIN キリンファミリーチャレンジカップ」が開催された。
キリンホールディングス株式会社と日本サッカー協会(JFA)が共同で開催したイベント。「年齢、性別、サッカー経験や障がいの有無にかかわらず、大人も子どもも一緒に楽しめる」ウォーキングフットボールイベントと
2024.05.28 21:15 Tue
26日、高円宮記念JFA夢フィールドにて「JFA×KIRIN キリンファミリーチャレンジカップ」が開催された。
キリンホールディングス株式会社と日本サッカー協会(JFA)が共同で開催したイベント。「年齢、性別、サッカー経験や障がいの有無にかかわらず、大人も子どもも一緒に楽しめる」ウォーキングフットボールイベントと
2024.05.28 21:15 Tue
 6月6日のアウェー・ミャンマー戦と11日の広島でのシリア戦に臨む日本代表26人が昨日24日に発表された。すでに2次予選は突破が決まっているため、国内組を中心にチームを作るプランもあったかもしれないが、森保一監督は海外組も含めてほぼベストメンバーを招集した。何事にも万全を期す、森保監督らしい人選と言える。
GKの前
2024.05.25 18:00 Sat
6月6日のアウェー・ミャンマー戦と11日の広島でのシリア戦に臨む日本代表26人が昨日24日に発表された。すでに2次予選は突破が決まっているため、国内組を中心にチームを作るプランもあったかもしれないが、森保一監督は海外組も含めてほぼベストメンバーを招集した。何事にも万全を期す、森保監督らしい人選と言える。
GKの前
2024.05.25 18:00 Sat
 FC町田ゼルビアから史上初となる日本代表選手が誕生した。
24日、日本サッカー協会(JFA)は2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選のミャンマー代表戦、シリア代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月から始まるアジア最終予選に向けた大事な2試合
2024.05.24 18:10 Fri
FC町田ゼルビアから史上初となる日本代表選手が誕生した。
24日、日本サッカー協会(JFA)は2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選のミャンマー代表戦、シリア代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月から始まるアジア最終予選に向けた大事な2試合
2024.05.24 18:10 Fri
 日本代表をキャプテンとして支えてきたMF長谷部誠。引退会見では、日本代表への想いも語った。
2002年からプロキャリアをスタートさせた長谷部。浦和の黄金時代を知り、ドイツに渡ってもヴォルフスブルクでブンデスリーガ制覇、フランクフルトではDFBポカールとヨーロッパリーグで優勝と、結果を残してきた。
日本代表と
2024.05.24 17:45 Fri
日本代表をキャプテンとして支えてきたMF長谷部誠。引退会見では、日本代表への想いも語った。
2002年からプロキャリアをスタートさせた長谷部。浦和の黄金時代を知り、ドイツに渡ってもヴォルフスブルクでブンデスリーガ制覇、フランクフルトではDFBポカールとヨーロッパリーグで優勝と、結果を残してきた。
日本代表と
2024.05.24 17:45 Fri
キリンチャレンジカップの関連記事
 キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
 ガーナ代表戦、ボリビア代表戦と続いた11月シリーズを、日本代表は2試合連続の無失点で締めくくった。その中心にいたのが、フィールドプレーヤーで唯一2試合フル出場を果たした33歳――谷口彰悟だ。2024年11月にアキレス腱を断裂。大怪我から戻ってきた男は、再び日本代表の最終ラインで存在感を放っている。2026年北中米ワール
2025.11.19 01:35 Wed
ガーナ代表戦、ボリビア代表戦と続いた11月シリーズを、日本代表は2試合連続の無失点で締めくくった。その中心にいたのが、フィールドプレーヤーで唯一2試合フル出場を果たした33歳――谷口彰悟だ。2024年11月にアキレス腱を断裂。大怪我から戻ってきた男は、再び日本代表の最終ラインで存在感を放っている。2026年北中米ワール
2025.11.19 01:35 Wed
 ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら
2025.11.19 00:45 Wed
ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら
2025.11.19 00:45 Wed
 ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦
2025.11.18 16:45 Tue
ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦
2025.11.18 16:45 Tue
 ガーナ戦のピッチに立った鹿島アントラーズの守護神・早川友基。正GK鈴木彩艶の負傷、第2GK大迫敬介の不在の中で巡ってきたチャンスを、無失点という最高の形で終えた。だが、試合後のミックスゾーンに現れた早川の表情に、満足の色はなかった。代表2戦目にして、“守るだけ”のGKでは終わらない次のステージを見据えていた。
■
2025.11.18 15:30 Tue
ガーナ戦のピッチに立った鹿島アントラーズの守護神・早川友基。正GK鈴木彩艶の負傷、第2GK大迫敬介の不在の中で巡ってきたチャンスを、無失点という最高の形で終えた。だが、試合後のミックスゾーンに現れた早川の表情に、満足の色はなかった。代表2戦目にして、“守るだけ”のGKでは終わらない次のステージを見据えていた。
■
2025.11.18 15:30 Tue
記事をさがす
|
|
遠藤航の人気記事ランキング

1
8万人収容のスタジアムが一気に解体…安全基準の問題でマレーシアのスタジアムを取り壊し、2029年までに新スタジアムに生まれ変わる
サッカーのスタジアムが崩れていく姿を見たことはあるだろうか。 かつてマレーシアで最大のスタジアムであった、シャー・アラム・スタジアムが取り壊された。 クアラルンプールの近郊にあるセランゴール州の州都であるシャー・アラム。その街にある最も有名なスタジアムの1つであるシャー・アラム・スタジアムは、8万372人の収容人数を誇る巨大スタジアムだった。 1994年にオープンしたスタジアムは、セランゴールFCの本拠地としても使用されており、アジアツアーで訪れるビッグクラブもプレー。チェルシーやアーセナル、バイエルンなどもプレーした。 国際大会でも使用された経験があり、1997年のワールドユース(現:U-20ワールドカップ)や2007年のアジアカップなどで使用。2015年のAFC U23選手権の予選では、U-22日本代表がプレーしており、遠藤航や浅野拓磨らリオ・デ・ジャネイロ・オリンピック世代の選手たちもプレーした。 しかし、2020年に老朽化やスタジアムの構造が安全基準を満たさないとして閉鎖。そしてついに破壊されることとなった。 一気にスタンドの屋根を落とす作業などが行われ、公開された動画では屋根が崩れ落ち、スタンドやピッチに落下していく様子が見て取れる。 スタジアムの解体工事は今年中に完了とのこと。2029年までに新たなスタジアムが建設される予定だ。 <span class="paragraph-title">【動画】珍しいスタジアム解体の瞬間…屋根が一気に崩壊</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a>: Malaysia's iconic Shah Alam stadium demolished in seconds.<a href="https://twitter.com/hashtag/Malaysia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Malaysia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ShahAlam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ShahAlam</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ShahAlamStadium?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ShahAlamStadium</a> <a href="https://t.co/cf6lSnZk8v">pic.twitter.com/cf6lSnZk8v</a></p>— TIMES NOW (@TimesNow) <a href="https://twitter.com/TimesNow/status/1839217883575943490?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.09.26 23:32 Thu
2
日本代表の背番号11/六川亨の日本サッカー見聞録
アジアカップはカタール代表の初優勝で終わり、5度目の戴冠を期待された日本代表は残念ながら準優勝に終わった。準決勝のイラン代表戦では今大会でベストのパフォーマンスから3-0の快勝を収めただけに、後手に回った決勝戦での前半の戦いぶりが悔やまれる。 そのカタール戦、ハーフタイムに控えの選手がピッチでボールを蹴っていたが、乾貴士と遠藤航の姿がなかった。0-2とリードされていただけに、「後半から乾と遠藤の2枚替えか。遠藤がボランチに戻れば守備を立て直すことができるが、体調は大丈夫なのか?」と期待したものの、森保一監督は動かなかった。 最初の交代カードは後半16分、原口元気に代えて武藤嘉紀を起用した。すると19分と21分に武藤が立て続けにヘッドでゴールを狙ったものの、シュートはクロスバーを越え、同点のチャンスを逃してしまった。決めていれば2011年カタール大会決勝の李忠成のようなヒーローになれただけに、武藤にとっては悔いの残るシュートだっただろう。 ただ、最初の交代カードで武藤を抜擢したが、彼の武器であるスピードはスペースがあってこと生きるタイプだ。カタールは自陣のゴール前を固めてカウンター狙いだったため、ゴールをこじ開けるにはクロスに対しガムシャラに飛び込む北川航也の方が効果的ではなかったかと疑問が残る。 それまで5試合に起用し、サブ組のFWでは最長の出場時間だっただけに、なぜ最後までベンチに温存したのか。北川が森保監督の期待に応えることができなかったと言われればそれまでだし、結果論にすぎないという反論もあることは百も承知だ。 そして改めて思うのは、北川は運がないということ。それは北川だけに限らず、今回彼が背負った日本代表の「背番号11」はなぜか結果に恵まれないということだ。 北川の前に「背番号11」を背負っていた選手が誰かと聞かれても、即答できるファンは数少ないのではないだろうか。ロシアW杯での「背番号11」は宇佐美貴史だったが、ほとんど活躍できなかった。 その前は豊田陽平であり、その前はというと柿谷曜一朗、原口元気、ハーフナー・マイク、前田遼一、玉田圭司、播戸竜二、佐藤寿人、巻誠一郎、鈴木隆行、黒部光昭、松井大輔、鈴木隆行、中山雅史、三浦淳寛、呂比須ワグナー、小野伸二、三浦知良らが「背番号11」を背負ってきた。 彼らの中で記憶に残るゴールを決めた選手となると、2002年日韓W杯の初戦ベルギー代表戦(2-2)で同点ゴールを決め、W杯で初めて勝点1をもたらした鈴木くらいではないだろうか。あとは“キング・カズ”の存在感が圧倒的だった。 もともと「背番号11」は左ウイングに与えられるナンバーだったものの、ポジションが流動化した現代サッカーでは9番と10番と同様に攻撃的な選手、ストライカーに与えられる番号でもある。にもかかわらず、日本代表の歴代「11番」は、カズ以降ストライカーとしての輝きを放てていない。 果たして3月に再招集される森保ジャパンにおいて、誰が「背番号11」を受け継ぐのか。そしてゴールという結果を出すことができるのか。23人のメンバーとともに注目したいと思っている。 2019.02.05 16:45 Tue
3
みんな気づいていた? プレミアリーグが中継時に使用する20クラブのゴールアニメーションを制作、各クラブを象徴したものに
新シーズンが開幕したプレミアリーグ。開幕節では、サウサンプトンの日本代表DF菅原由勢、クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が共にデビューを果たし、通算15名の日本人がプレーしたこととなった。 加えて、ブライトン&ホーヴ・アルビオンの日本代表MF三笘薫が見事な開幕ゴールを記録。チームの勝利に貢献し、プレミアリーグの週間ベストイレブンにも選出されるなど、話題に事欠かなかった。 また、5連覇を目指すマンチェスター・シティや2年連続2位のアーセナル、リバプールやマンチェスター・ユナイテッドなどは順調に勝利した一方で、チェルシーはシティに敗戦。トッテナムは昇格組のレスター・シティ相手にドローとなるなど、開幕節から盛り上がりを見せた。 そのプレミアリーグだが、今シーズンから新たな取り組みを行っている事を知っているだろうか。すでに話題にもあがり、気がついている人も多数いるが、試合中継時に工夫がされている。 それは、ゴールが決まった際のアニメーション。試合中継の画面左上には、両クラブのスコアが並んでいることはご存じだろうが、得点が決まればスコアが変わり、試合の時間や交代選手の情報、退場者がいる場合にはレッドカードがつくなど、試合情報がまとまっている。 プレミアリーグは、今シーズン全20クラブ用にゴール時のアニメーションを作成。得点が入った際に、そのクラブのエンブレムをモチーフにしたアニメーションが流れている。 例えば、開幕戦でいきなりゴールを決めた三笘。三笘がゴールを決めた際にも使用されたが、ブライトンはエンブレムにいるカモメが飛んできてゴールを祝うこととなる。 鎌田が所属するクリスタル・パレスであれば、エンブレムにいる鷲がボールを運びながら、「GOAL」の「O」にボールを置いていくというアニメーションだ。 冨安健洋が所属するアーセナルであればエンブレムの大砲が放たれ、「GOAL」の文字が登場。遠藤航が所属するリバプールは、「ライバー・バード」が門のように開く仕様に。菅原のサウサンプトンは「GOAL」の文字に天使の羽と輪がついて飛んでいくというものだ。 各クラブのエンブレムに合わせたアニメーション。ゴールが決まった際には、スコアのところを一度注目して見ても楽しめるはずだ。 <div style="text-align:center;" id="cws_ad"><hr /><a href="https://www.video.unext.jp/lp/football_pack?adid=XXX&utm_medium=a_n&utm_campaign=a_n&cid=D34327&utm_source=seesawgame_ultrasoccer&utm_term=ultrasoccer&rid=SG00003" target="_blank">プレミアリーグを見るなら<br />「U-NEXTサッカーパック」がお得!!</a><hr /></div> <span class="paragraph-title">【動画】全20クラブをチェック! プレミアリーグが20クラブのゴールアニメーションを作成!</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"><br><br>Got a favourite? <a href="https://t.co/3ZbuZBtWzS">pic.twitter.com/3ZbuZBtWzS</a></p>— Premier League (@premierleague) <a href="https://twitter.com/premierleague/status/1826303350876336488?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <div style="text-align:center;" id="cws_ad"><hr /><a href="https://www.video.unext.jp/lp/football_pack?adid=XXX&utm_medium=a_n&utm_campaign=a_n&cid=D34327&utm_source=seesawgame_ultrasoccer&utm_term=ultrasoccer&rid=SG00003" target="_blank">プレミアリーグを見るなら<br />「U-NEXTサッカーパック」がお得!!</a><hr /></div> 2024.08.22 12:33 Thu
4
「すげー親近感湧く」遠藤航の同僚コナテのSNSに日本のアニメキャラクターが登場「本当に大好きなんだな」
リバプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテのアニメ愛が話題だ。 17日、プレミアリーグ第25節でブレントフォードとアウェイで対戦したリバプール。サスペンション明けのコナテは先発に復帰してフル出場し、チームの1-4の大勝に貢献していた。 試合後、コナテはインスタグラムを更新。ブレントフォード戦の勝利をファンに報告するとともに「戦いは続く」と今後の戦いへさらに気を引き締めていた。 コナテは、ブレントフォード戦で共にフル出場した日本代表MF遠藤航との2ショットをアップ。2人が笑顔で肩を組む姿は日本人としても微笑ましいが、もう1つの投稿がさらに日本のファンを沸かせることになった。 飛行機の翼の画像と合わせて投稿されたのは、日本の大人気漫画『進撃の巨人』に登場する調査兵団のリヴァイ・アッカーマン兵長が、胸に拳を当てるポーズを取っている画像だった。このポーズは、調査兵団の中で「公に心臓を捧げる決意」を表す敬礼のようなもので、『心臓を捧げよ』の言葉とともにポーズが取られる。 コナテは以前から日本の漫画やアニメ好きとして知られており、過去にも自身のSNSで『進撃の巨人』にまつわる投稿をしたことも。遠藤がリバプールに加入して早々の頃には、「遠藤にかめはめ波を出す秘訣を教えてくれたのさ!」とこちらも日本の人気の漫画『ドラゴンボール』で仲良くなっていた。 コナテの投稿には、ファンも「すげー親近感湧く」、「心臓を捧げよ!!」、「コナテ、遠藤、アニメより良いトリオはない」、「本当に大好きなんだな」とコメント。一方で、コナテの画像が反転していたことから、「それだと逆なんだが」といったツッコミも寄せられていた。 <span class="paragraph-title">【画像】コナテのSNSに日本のアニメキャラクターが登場(3枚目)</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/C3dHP29IPpX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/C3dHP29IPpX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/C3dHP29IPpX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">@ibrahimakonateがシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> 2024.02.20 12:00 Tue
5
日本代表のスタメン発表!両ウイングバックは堂安律&三笘薫…初招集の大橋祐紀はベンチ入り【2026W杯アジア最終予選】
サウジアラビア代表戦に臨む日本代表のスターティングイレブンが発表された。 10日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選の第3節で日本はアウェイでサウジアラビアと対戦する。 9月に行われた中国代表戦、バーレーン代表戦で大勝での連勝スタートを切った日本。過去一度も勝ったことがないアウェイでのサウジアラビア戦に臨む。 森保一監督は9月に引き続き[3-4-2-1]のシステムを採用。GKに鈴木彩艶(パルマ)、3バックに板倉滉(ボルシアMG)、谷口彰悟(シント=トロイデン)、町田浩樹(ユニオン・サン=ジロワーズ)を起用した。 ボランチには遠藤航(リバプール)と守田英正(スポルティングCP)を起用し、ウイングバックには堂安律(フライブルク)と三笘薫(ブライトン&ホーヴ・アルビオン)を起用。2シャドーに鎌田大地(クリスタル・パレス)と南野拓実(モナコ)、トップに上田綺世(フェイエノールト)と並んだ。 なお、DF長友佑都(FC東京)、DF関口大輝(柏レイソル)、DF望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)、MF藤田譲瑠チマ(シント=トロイデン)がメンバー外。初招集のFW大橋祐紀(ブラックバーン)はベンチ入りを果たしている。 サウジアラビア代表戦は10日(木)の27時にキックオフ。DAZNが独占ライブ配信する。 ◆日本代表スターティングメンバー GK 鈴木彩艶(パルマ) DF 板倉滉(ボルシアMG) 谷口彰悟(シント=トロイデン) 町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ) MF 遠藤航(リバプール) 守田英正(スポルティングCP) 三笘薫(ブライトン&ホーヴ・アルビオン) 南野拓実(モナコ) 堂安律(フライブルク) 鎌田大地(クリスタル・パレス) FW 上田綺世(フェイエノールト) ◆ベンチ入り GK 大迫敬介(サンフレッチェ広島) 谷晃生(FC町田ゼルビア) DF 菅原由勢(サウサンプトン) 瀬古歩夢(グラスホッパー) MF 堂安律(フライブルク) 田中碧(リーズ・ユナイテッド) 久保建英(レアル・ソシエダ) FW 前田大然(セルティック) 中村敬斗(スタッド・ランス) 小川航基(NECナイメヘン) 大橋祐紀(ブラックバーン) ◆メンバー外 DF 長友佑都(FC東京) 望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア) 関口大輝(柏レイソル) MF 藤田譲瑠チマ(シント=トロイデン) 2024.10.11 02:19 Fri日本の人気記事ランキング

1
「まさに死闘ってカンジ」歴史に残るバーレーンとの4-3の激闘!2004年大会プレイバックに反響「このゴールで中澤佑二に惚れた」
31日、日本代表はアジアカップ2023のラウンド16でバーレーン代表と対戦する。 過去の対戦成績は日本の8勝2敗となっているが、アジアカップの舞台で最後に対戦したのは2004年の中国大会での準決勝。記憶に残る激闘だった。 MF小野伸二、FW高原直泰ら当時の主力選手が欠場していた当時の日本は、開催国の中国サポーターにブーイングを浴びせられながらも決勝トーナメントに進出すると、準々決勝ではPK戦途中でのサイド変更とGK川口能活の神がかり的なセーブが印象深いヨルダン代表戦に勝利し、準決勝でバーレーンと対戦した。 しかし、バーレーン戦では開始6分に先制ゴールを許すと、40分にはMF遠藤保仁が不可解な判定で一発退場。日本はビハインドの状況で数的不利を負ってしまった。 数的不利の状況でもMF中田浩二とFW玉田圭司のゴールで逆転した日本だったが、その後2失点。2-3と1点ビハインドで試合終盤を迎えた。 それでも日本は最後まで諦めず。DFも攻めあがって同点ゴールを狙うと、90分にDF中澤佑二が値千金の同点ゴール。不屈の精神で同点に追いつくと、延長前半には玉田の独走ゴールが決まり、4-3で激闘を制していた。 なんとか決勝に進出した日本は、決勝で中国代表を撃破。見事に大会連覇を成し遂げていた。 久しぶりの対戦を前に『DAZN』は当時の試合映像をプレイバック。SNS上のファンも「このゴールで中澤佑二に惚れた」、「バーレーン戦といえばこの試合よな」、「痺れたね、玉田」、「まさに「死闘」ってカンジだった!」、「2004の大会は激熱だった」と当時を思い返している。 ベスト8を懸けた一戦は、31日の20時30分にキックオフ。『DAZN』で視聴が可能だ。 <span class="paragraph-title">【動画】当時の記憶が蘇る!2004年大会でのバーレーンとの激闘ハイライト</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ja" dir="ltr">/<br>「バーレーンvs日本」<br>過去対戦をプレイバック<br>\<br><br>アジアカップ2004年大会で起きた<br>奇跡の大逆転劇<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/AFC%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AFCアジアカップ</a> ラウンド16<br>バーレーン×日本<br>1/31(水)20:30(19:45配信開始)<br><a href="https://twitter.com/hashtag/DAZN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DAZN</a> 独占配信<br>出演:水沼貴史/小野伸二/佐藤寿人/下田恒幸/桑原学 <a href="https://t.co/x7Sals8iKu">pic.twitter.com/x7Sals8iKu</a></p>— DAZN Japan (@DAZN_JPN) <a href="https://twitter.com/DAZN_JPN/status/1752609401201189348?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.01.31 18:45 Wed
2
「何度見ても鳥肌」ブラジルW杯出場を掴んだ本田圭佑の豪州戦“ど真ん中PK”にファン大興奮「やっぱメンタル強すぎ」
7大会連続7度目のワールドカップ(W杯)出場を懸けて、最終予選のラスト2試合を戦う日本代表。24日には出場を争うオーストラリア代表との大一番を控えている。 そんな中、日本サッカー協会(JFA)の公式SNSが2014年のブラジルW杯出場を決めたオーストラリア戦でのMF本田圭佑のPKに再び焦点を当てている。 当時、アルベルト・ザッケローニ監督のもとで5大会連続のW杯出場を目指した日本は、MF本田圭佑、MF香川真司、FW岡崎慎司ら海外組を主軸に、最終予選で4勝1分けと好発進。早くも予選突破に王手をかけると、ヨルダンとのアウェイゲームに敗れるという波乱もあったものの、オーストラリアとのホームゲームに臨む。 試合終盤の82分に失点を許す厳しい展開となったが、後半アディショナルタイムにPKを獲得。そのキッカーを本田が務めた。 ゴールマウスにはオーストラリアの守護神マーク・シュウォーツァー。緊張感の漂うなか、本田は大きく息を吐いてから助走をスタート。左足のPKをど真ん中に蹴り込むと、埼玉スタジアム2002のスタンドからは轟音のような歓声が鳴り響いた。 試合はこのまま1-1の引き分けとなり、日本は開催国ブラジルを除いて最速でのW杯本大会出場を決めていた。 このタイミングで本田のPKシーンをJFAが公開したところ、多くのファンが反応。「最高でした」、「やっぱこのPKを蹴れるってメンタル強すぎだな」、「この瞬間は一生忘れないと思う」、「何度見ても鳥肌立つ 何度見ても感動する」といったコメントが寄せられており、多くの人の記憶に刻まれているようだ。 日本はこのブラジル大会だけでなく、2018年のロシア大会のアジア最終予選でもオーストラリア戦でW杯出場の切符を手にしている。24日の試合で勝利すればその時点でカタールへの切符を手にすることとなるが、この大一番を制することはできるだろうか <span class="paragraph-title">【動画】何度でも見られる! 本田圭佑がど真ん中に決めたW杯出場を決めるPK</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">日本サッカー協会(JFA)/日本代表/なでしこジャパン(@japanfootballassociation)がシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> 2022.03.22 20:30 Tue
3
「素晴らしいムービーありがとう」W杯の熱量そのままに!開幕へ向けたJリーグのPVが大反響「四年後じゃない。二ヶ月後だ」
ワールドカップ(W杯)の熱気を冷ましてしまうのはもったいない。 日本代表の活躍も記憶に新しいカタールW杯はアルゼンチン代表の優勝で閉幕したが、サッカーファンにはとっては高校サッカー、インカレ、皇后杯など、まだまだイベントが続く。 23日には来季のJリーグ開幕節の日程も発表に。さらにJリーグは翌日、公式SNSで開幕へ向けたプロモーションビデオを公開した。 各W杯戦士がJリーグチームに在籍していた際の懐かしいユニフォームをファンが着用し、試合を注視。さらに当時の映像に加え、ラストにはサプライズも盛り込まれてる。 「Jリーグから巣立った選手たちが、カタールで戦っていた。」 「祭りが終わって、もうすぐ日常が始まる。」 「次の主役たちは、たぶん、私たちの日常の中にいる。もしかしたら、いつものスタジアムのピッチに。」 「また、ここから始めよう。」 「四年後じゃない。二ヶ月後だ。」 「2023年2月17日、Jリーグ開幕。」 近年では新卒で海外挑戦をする選手や海外クラブの育成組織へ加入するプレーヤーも増加しているが、カタールW杯を戦った日本代表26選手は全員がJリーグ経験者。中にはJ3でのプレー経験を持つ選手もいる。 過去から未来へとつながる映像には、ファンからも「素晴らしいムービーありがとうございます」、「感動したわ」、「泣かせますやん」、「2ヶ月後とか待ちきれないな」などの声が届けられたほか、現役選手やOBからも大きな反響が寄せられている。 <span class="paragraph-title">【動画】Jリーグ開幕へ向けた煽りPV</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="A32xw6cPO3w";var video_start = 0;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2022.12.24 15:50 Sat
4
「爽やか〜」「かっこよすぎ」田中碧のニューヘアーが大絶賛、大先輩も「髪型グーやん」
デュッセルドルフに所属する日本代表MF田中碧の髪型が大きな注目を集めている。 すでにドイツに戻っている田中は、デュッセルドルフのチーム写真に参加。新ユニフォームを身に纏って撮影に臨んでいた。 その田中は、日本に滞在していた際に国立競技場で行われた高級時計ブランド「HUBLOT」のイベントに参加。スーツ姿で臨んだ。 このイベントには日本代表の森保一監督なども参加。田中は川崎フロンターレ時代のチームメイトであり日本代表でも共に戦っているDF板倉滉との2ショットも投稿していた。 その田中の投稿で注目されたのが新たな髪型。川崎Fの先輩であるFW小林悠は「髪型グーやん」とコメント。日本代表のチームメイトであるMF鎌田大地もキスをする絵文字を投稿した。 また、ファンも髪型に注目。「髪型似合いすぎ」、「前髪を上げるのもカッコイイ」、「かっこよすぎ」、「めっちゃ似合ってます」、「爽やか〜」と称賛の声が集まった。 田中といえば、前髪を下ろした姿が定番で、おでこが見えていることはなかなか珍しい。スーツ姿と相まって、新たな髪型は好評だったようだ。 <span class="paragraph-title">【写真】大先輩もファンも大絶賛の新たな髪型</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CfYrJ5TuHRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CfYrJ5TuHRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CfYrJ5TuHRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ao Tanaka / 田中 碧(@tnk_0910)がシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> 2022.07.01 21:50 Fri
5