 明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。
リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ
2025.05.17 18:20 Sat
明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。
リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ
2025.05.17 18:20 Sat
インサイドハーフの新たな可能性…原口元気、鎌田大地という選択肢が持つ意味/日本代表コラム
2022.06.06 06:40 Mon

世界一のチームと言っても良いブラジルと対戦する日本代表。これまで12試合を戦い、2分け10敗と歯が立っていない。
しかし、ワールドカップ(W杯)開催の年に、それも大会に向けた準備が進んでいる段階で対戦するのは初めて。今まで以上に、豪華な主軸が顔を並べている。
カタールW杯では、日本はドイツ代表、スペイン代表と世界でも有数の強豪国とグループステージで同居している。いわゆる、“死の組”と言われても良いようなグループだ。
もう1チームはニュージーランド代表かコスタリカ代表かはまだ決定していないが、下馬評はドイツとスペインの勝ち上がりであることは間違いない。実力的に考えても当然の結果と言える。
しかし、その壁を打ち破るべく日本は準備。「ワールドカップでベスト8」という目標を掲げているが、その目標を達成するには遅かれ早かれ、世界の強豪国と対戦することにはなる。
その中で1つポイントとして見たいのが、インサイドハーフの選択だ。
2日に行われたキリンチャレンジカップ2022のパラグアイ代表戦では、控えメンバーが中心となり、原口元気(ウニオン・ベルリン)と鎌田大地(フランクフルト)がインサイドハーフで起用された。
7大会連続7度目のW杯出場に黄信号が灯った日本は、それまでの[4-2-3-1]から[4-3-3]にシステムを変更。それに伴い、インサイドハーフには守田英正(サンタ・クララ)と田中碧(デュッセルドルフ)を起用。アンカーの遠藤航(シュツットガルト)との3人の中盤で守備の強度をあげ、中盤を制圧することに成功した。
この3人は、元々ボランチでプレーしており、守備の強度が高く、運動量も豊富。さらに、後方からのビルドアップの能力に長けており、ポジションを前後しながらも互いに補完しあい、チームとしてスムーズにビルドアップして流れを掴むことができていた。
ボールを握る時間が長くなるアジアでの戦いには確かに適しており、中盤で守備強度をあげ、奪って一気にカウンターという戦い方も合っていた。サウジアラビア代表やオーストラリア代表といったアジアの強豪に手こずることが多かった日本だが、[4-3-3]が成熟した結果、今まで以上にコントロールでき、アウェイでのオーストラリア戦初勝利でカタールW杯行きを決めたということからも、安定感が増したことはわかる。
ただ、世界の強豪と戦う上では、それだけでは物足りないと言える。
確かにビルドアップ能力だけでなく、守田も田中もポジショニングが優れていたり、それぞれの特徴を持っている。しかし、ボールを握る時間は強豪相手には確実に減る。さらに、ビルドアップも思うようにさせてもらえないだろう。中盤の強度という点では五分に近い形で戦える可能性はあるが、アジア仕様の人選と言える可能性もある。
そこで注目したいのがパラグアイ戦でプレーした2人。クラブではインサイドハーフでもプレーしながら、代表ではほとんど試されることがなかった。いや、試せる状況でもなかったと言えるのかもしれない。
ただ、原口はレギュラーとして1年間戦い、ウニオン・ベルリンはブンデスリーガで5位フィニッシュ。鎌田も決定的な仕事が増え、特に優勝したヨーロッパリーグでは数字も残していた。
この2人、今回の合宿ではトレーニングでも常にと言って良いほど横にいて、よく話したり絡んでいる姿を見た。さらに、クラブでの充実感から来るものなのか、顔つきがこれまでの代表活動とは違い、鎌田は自信がついたのかリラックスしながらも精悍な顔つきに、原口も闘志を秘めた良い顔をしていた。
その結果、パラグアイ戦で原口は2アシスト、鎌田は1ゴール1アシストを記録。インサイドハーフでもパフォーマンスが出せることを示しただけでなく、日本にとって新たなパターンを生み出す可能性を見せたのだ。
守田、田中に比べ、確実に前のポジションでのプレー経験が多い原口と鎌田は、攻撃面で圧倒的に違いを出せることを証明した。ボックス付近で絡むだけでなく、ボックス内にまで入っていくプレーを何度となく行い、ゴールに近いポジションでプレーするという、本来インサイドハーフに求められるプレーを見せた。
そこで言えるのが、戦い方を相手によって変えるために、インサイドハーフの組み合わせを変えるということだ。
ビルドアップ力に長け、守備の強度を高められる守田と田中、ボックス内でのプレーも厭わず、より攻撃に絡むことが得意な原口と鎌田。この4人が組み合うことができると大きな作用が生まれるはずだ。
パラグアイ戦の後半途中に選手交代の流れで鎌田と田中がインサイドで組む時間があった。田中は森田に比べてパスで局面を変えることができ、攻撃への判断が早いため、ボックス付近にポジションをとった鎌田を生かしていた。また、ミドルシュートでゴールを決めた田中だが、そのパスを送ったのは鎌田。互いの特徴を理解し、ポジションを取れれば、いつもと違う組み合わせでも結果を出せるのだ。
また、ボールを保持する時間が減り、ビルドアップも簡単に行かないことが想像される強豪国との対戦では、奪ってからのショートカウンターという選択肢もある。守備強度の高い2人を使って奪う力を増すのか、攻撃的にプレーできる2人を使って、よりカウンターの推進力を増すのか。最終予選では試せなかった戦い方のトライをぜひ見てみたい。
ブラジル相手にも攻撃タイプのインサイドハーフが通用するのかは、限られた時間帯でも見て見たいものだ。
《超ワールドサッカー編集部・菅野剛史》
しかし、ワールドカップ(W杯)開催の年に、それも大会に向けた準備が進んでいる段階で対戦するのは初めて。今まで以上に、豪華な主軸が顔を並べている。
カタールW杯では、日本はドイツ代表、スペイン代表と世界でも有数の強豪国とグループステージで同居している。いわゆる、“死の組”と言われても良いようなグループだ。
しかし、その壁を打ち破るべく日本は準備。「ワールドカップでベスト8」という目標を掲げているが、その目標を達成するには遅かれ早かれ、世界の強豪国と対戦することにはなる。
その大きな2試合を前に、ブラジルと対戦できることは、現在地を測るという意味でも非常に大きい。そして、何が通用し、何が通用しないのか。どの戦い方ならば勝機が見出せるのかを見つけるにも良い機会と言えるだろう。
その中で1つポイントとして見たいのが、インサイドハーフの選択だ。
2日に行われたキリンチャレンジカップ2022のパラグアイ代表戦では、控えメンバーが中心となり、原口元気(ウニオン・ベルリン)と鎌田大地(フランクフルト)がインサイドハーフで起用された。
7大会連続7度目のW杯出場に黄信号が灯った日本は、それまでの[4-2-3-1]から[4-3-3]にシステムを変更。それに伴い、インサイドハーフには守田英正(サンタ・クララ)と田中碧(デュッセルドルフ)を起用。アンカーの遠藤航(シュツットガルト)との3人の中盤で守備の強度をあげ、中盤を制圧することに成功した。
この3人は、元々ボランチでプレーしており、守備の強度が高く、運動量も豊富。さらに、後方からのビルドアップの能力に長けており、ポジションを前後しながらも互いに補完しあい、チームとしてスムーズにビルドアップして流れを掴むことができていた。
ボールを握る時間が長くなるアジアでの戦いには確かに適しており、中盤で守備強度をあげ、奪って一気にカウンターという戦い方も合っていた。サウジアラビア代表やオーストラリア代表といったアジアの強豪に手こずることが多かった日本だが、[4-3-3]が成熟した結果、今まで以上にコントロールでき、アウェイでのオーストラリア戦初勝利でカタールW杯行きを決めたということからも、安定感が増したことはわかる。
ただ、世界の強豪と戦う上では、それだけでは物足りないと言える。
確かにビルドアップ能力だけでなく、守田も田中もポジショニングが優れていたり、それぞれの特徴を持っている。しかし、ボールを握る時間は強豪相手には確実に減る。さらに、ビルドアップも思うようにさせてもらえないだろう。中盤の強度という点では五分に近い形で戦える可能性はあるが、アジア仕様の人選と言える可能性もある。
そこで注目したいのがパラグアイ戦でプレーした2人。クラブではインサイドハーフでもプレーしながら、代表ではほとんど試されることがなかった。いや、試せる状況でもなかったと言えるのかもしれない。
ただ、原口はレギュラーとして1年間戦い、ウニオン・ベルリンはブンデスリーガで5位フィニッシュ。鎌田も決定的な仕事が増え、特に優勝したヨーロッパリーグでは数字も残していた。
この2人、今回の合宿ではトレーニングでも常にと言って良いほど横にいて、よく話したり絡んでいる姿を見た。さらに、クラブでの充実感から来るものなのか、顔つきがこれまでの代表活動とは違い、鎌田は自信がついたのかリラックスしながらも精悍な顔つきに、原口も闘志を秘めた良い顔をしていた。
その結果、パラグアイ戦で原口は2アシスト、鎌田は1ゴール1アシストを記録。インサイドハーフでもパフォーマンスが出せることを示しただけでなく、日本にとって新たなパターンを生み出す可能性を見せたのだ。
守田、田中に比べ、確実に前のポジションでのプレー経験が多い原口と鎌田は、攻撃面で圧倒的に違いを出せることを証明した。ボックス付近で絡むだけでなく、ボックス内にまで入っていくプレーを何度となく行い、ゴールに近いポジションでプレーするという、本来インサイドハーフに求められるプレーを見せた。
そこで言えるのが、戦い方を相手によって変えるために、インサイドハーフの組み合わせを変えるということだ。
ビルドアップ力に長け、守備の強度を高められる守田と田中、ボックス内でのプレーも厭わず、より攻撃に絡むことが得意な原口と鎌田。この4人が組み合うことができると大きな作用が生まれるはずだ。
パラグアイ戦の後半途中に選手交代の流れで鎌田と田中がインサイドで組む時間があった。田中は森田に比べてパスで局面を変えることができ、攻撃への判断が早いため、ボックス付近にポジションをとった鎌田を生かしていた。また、ミドルシュートでゴールを決めた田中だが、そのパスを送ったのは鎌田。互いの特徴を理解し、ポジションを取れれば、いつもと違う組み合わせでも結果を出せるのだ。
また、ボールを保持する時間が減り、ビルドアップも簡単に行かないことが想像される強豪国との対戦では、奪ってからのショートカウンターという選択肢もある。守備強度の高い2人を使って奪う力を増すのか、攻撃的にプレーできる2人を使って、よりカウンターの推進力を増すのか。最終予選では試せなかった戦い方のトライをぜひ見てみたい。
ブラジル相手にも攻撃タイプのインサイドハーフが通用するのかは、限られた時間帯でも見て見たいものだ。
《超ワールドサッカー編集部・菅野剛史》
原口元気の関連記事
 明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。
リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ
2025.05.17 18:20 Sat
明治安田J1リーグ第17節の浦和レッズvsFC東京が17日に埼玉スタジアム2002で行われ、3-2でホームの浦和が勝利した。
リーグ戦2試合未勝利となっている4位浦和(勝ち点26)は、ドローで終えた前節のアルビレックス新潟戦からスタメンを4人変更。金子拓郎や松本泰志、長沼洋一、GK牲川歩見に代えて大久保智明、サミ
2025.05.17 18:20 Sat
 11日、明治安田J1リーグ第16節のアルビレックス新潟vs浦和レッズがデンカビッグスワンスタジアムで行われた。
18位と降格圏に沈む新潟と、5連勝がストップした4位の浦和の対戦に。立ち位置が大きく異なる両者の対戦となる中で、新潟は直近の試合から5名を変更。 稲村隼翔、堀米悠斗、小見洋太、秋山裕紀、小野裕二が外れ、
2025.05.11 16:00 Sun
11日、明治安田J1リーグ第16節のアルビレックス新潟vs浦和レッズがデンカビッグスワンスタジアムで行われた。
18位と降格圏に沈む新潟と、5連勝がストップした4位の浦和の対戦に。立ち位置が大きく異なる両者の対戦となる中で、新潟は直近の試合から5名を変更。 稲村隼翔、堀米悠斗、小見洋太、秋山裕紀、小野裕二が外れ、
2025.05.11 16:00 Sun
 3日、明治安田J1リーグ第14節の浦和レッズvs東京ヴェルディが埼玉スタジアム2002で行われ、ホームの浦和が2-0で勝利した。
4位の浦和は前節、サンフレッチェ広島を1-0で破って4連勝を達成。川崎フロンターレのACLE参戦に伴い第13節が後ろ倒し開催となる影響で中7日と休養十分で臨んだ今節は2016年以来のリ
2025.05.03 17:06 Sat
3日、明治安田J1リーグ第14節の浦和レッズvs東京ヴェルディが埼玉スタジアム2002で行われ、ホームの浦和が2-0で勝利した。
4位の浦和は前節、サンフレッチェ広島を1-0で破って4連勝を達成。川崎フロンターレのACLE参戦に伴い第13節が後ろ倒し開催となる影響で中7日と休養十分で臨んだ今節は2016年以来のリ
2025.05.03 17:06 Sat
 20日、明治安田J1リーグ第11節の浦和レッズvs横浜F・マリノスが埼玉スタジアム2002で行われた。
浦和は現在連勝中。FC町田ゼルビア、京都サンガF.C.と上位を相手に勝ち点を重ねた中、ミッドウィークの京都戦と同じメンバーで臨んだ。
対する横浜FMは、ミッドウィークは清水エスパルスに2-3で逆転負け。2
2025.04.20 18:04 Sun
20日、明治安田J1リーグ第11節の浦和レッズvs横浜F・マリノスが埼玉スタジアム2002で行われた。
浦和は現在連勝中。FC町田ゼルビア、京都サンガF.C.と上位を相手に勝ち点を重ねた中、ミッドウィークの京都戦と同じメンバーで臨んだ。
対する横浜FMは、ミッドウィークは清水エスパルスに2-3で逆転負け。2
2025.04.20 18:04 Sun
 13日、明治安田J1リーグ第10節、FC町田ゼルビアvs浦和レッズが国立競技場で行われ、アウェイの浦和が0-2で勝利した。
首位の町田は前節、川崎フロンターレとの上位対決で2-2のドロー。続くYBCルヴァンカップ2回戦ではJ2のヴァンフォーレ甲府を1-0で下した。J1でクラブ史上初の7戦無敗を期して臨んだ国立開催
2025.04.13 16:08 Sun
13日、明治安田J1リーグ第10節、FC町田ゼルビアvs浦和レッズが国立競技場で行われ、アウェイの浦和が0-2で勝利した。
首位の町田は前節、川崎フロンターレとの上位対決で2-2のドロー。続くYBCルヴァンカップ2回戦ではJ2のヴァンフォーレ甲府を1-0で下した。J1でクラブ史上初の7戦無敗を期して臨んだ国立開催
2025.04.13 16:08 Sun
日本の関連記事
 東京ヴェルディとの試合を行うために来日したレアル・ソシエダ。28日には試合前日のトレーニングを行った。
25日にラ・リーガ最終節を戦い、27日に来日。ハードなスケジュールの中での来日となったが、選手たちはリラックスムードでトレーニングに臨んだ。
トレーニング前にはメディアの取材にイマノル・アルグアシル監督、
2024.05.28 23:15 Tue
東京ヴェルディとの試合を行うために来日したレアル・ソシエダ。28日には試合前日のトレーニングを行った。
25日にラ・リーガ最終節を戦い、27日に来日。ハードなスケジュールの中での来日となったが、選手たちはリラックスムードでトレーニングに臨んだ。
トレーニング前にはメディアの取材にイマノル・アルグアシル監督、
2024.05.28 23:15 Tue
 26日、高円宮記念JFA夢フィールドにて「JFA×KIRIN キリンファミリーチャレンジカップ」が開催された。
キリンホールディングス株式会社と日本サッカー協会(JFA)が共同で開催したイベント。「年齢、性別、サッカー経験や障がいの有無にかかわらず、大人も子どもも一緒に楽しめる」ウォーキングフットボールイベントと
2024.05.28 21:15 Tue
26日、高円宮記念JFA夢フィールドにて「JFA×KIRIN キリンファミリーチャレンジカップ」が開催された。
キリンホールディングス株式会社と日本サッカー協会(JFA)が共同で開催したイベント。「年齢、性別、サッカー経験や障がいの有無にかかわらず、大人も子どもも一緒に楽しめる」ウォーキングフットボールイベントと
2024.05.28 21:15 Tue
 6月6日のアウェー・ミャンマー戦と11日の広島でのシリア戦に臨む日本代表26人が昨日24日に発表された。すでに2次予選は突破が決まっているため、国内組を中心にチームを作るプランもあったかもしれないが、森保一監督は海外組も含めてほぼベストメンバーを招集した。何事にも万全を期す、森保監督らしい人選と言える。
GKの前
2024.05.25 18:00 Sat
6月6日のアウェー・ミャンマー戦と11日の広島でのシリア戦に臨む日本代表26人が昨日24日に発表された。すでに2次予選は突破が決まっているため、国内組を中心にチームを作るプランもあったかもしれないが、森保一監督は海外組も含めてほぼベストメンバーを招集した。何事にも万全を期す、森保監督らしい人選と言える。
GKの前
2024.05.25 18:00 Sat
 FC町田ゼルビアから史上初となる日本代表選手が誕生した。
24日、日本サッカー協会(JFA)は2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選のミャンマー代表戦、シリア代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月から始まるアジア最終予選に向けた大事な2試合
2024.05.24 18:10 Fri
FC町田ゼルビアから史上初となる日本代表選手が誕生した。
24日、日本サッカー協会(JFA)は2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選のミャンマー代表戦、シリア代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月から始まるアジア最終予選に向けた大事な2試合
2024.05.24 18:10 Fri
 日本代表をキャプテンとして支えてきたMF長谷部誠。引退会見では、日本代表への想いも語った。
2002年からプロキャリアをスタートさせた長谷部。浦和の黄金時代を知り、ドイツに渡ってもヴォルフスブルクでブンデスリーガ制覇、フランクフルトではDFBポカールとヨーロッパリーグで優勝と、結果を残してきた。
日本代表と
2024.05.24 17:45 Fri
日本代表をキャプテンとして支えてきたMF長谷部誠。引退会見では、日本代表への想いも語った。
2002年からプロキャリアをスタートさせた長谷部。浦和の黄金時代を知り、ドイツに渡ってもヴォルフスブルクでブンデスリーガ制覇、フランクフルトではDFBポカールとヨーロッパリーグで優勝と、結果を残してきた。
日本代表と
2024.05.24 17:45 Fri
キリンチャレンジカップの関連記事
 キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
キックオフ直後から、気合という燃料を積んでいることは明らかだった。このチャンスを、モノにしてやるんだ。攻守両面でのアグレッシブなプレーから、この試合に懸ける思いは全身から溢れ出ていた。タフに右サイドを守りながら、同学年のMF久保建英と一緒に決定機も演出した。サイドバックを本職とする選手が生み出すハーモニーが顔を覗かせて
2025.11.20 21:00 Thu
 ガーナ代表戦、ボリビア代表戦と続いた11月シリーズを、日本代表は2試合連続の無失点で締めくくった。その中心にいたのが、フィールドプレーヤーで唯一2試合フル出場を果たした33歳――谷口彰悟だ。2024年11月にアキレス腱を断裂。大怪我から戻ってきた男は、再び日本代表の最終ラインで存在感を放っている。2026年北中米ワール
2025.11.19 01:35 Wed
ガーナ代表戦、ボリビア代表戦と続いた11月シリーズを、日本代表は2試合連続の無失点で締めくくった。その中心にいたのが、フィールドプレーヤーで唯一2試合フル出場を果たした33歳――谷口彰悟だ。2024年11月にアキレス腱を断裂。大怪我から戻ってきた男は、再び日本代表の最終ラインで存在感を放っている。2026年北中米ワール
2025.11.19 01:35 Wed
 ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら
2025.11.19 00:45 Wed
ゴール前で輝く決定力と、中盤を支える戦術眼。その両方を併せ持つ“新しいボランチ像”を、日本代表のMF鎌田大地がボリビア代表戦で体現した。開始4分、MF久保建英のクロスを胸で収め、左足で冷静に流し込んだ先制点。ボランチでありながらペナルティエリアへ侵入し、フィニッシュまで持ち込む――。クリスタルパレスと日本代表では求めら
2025.11.19 00:45 Wed
 ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦
2025.11.18 16:45 Tue
ガーナ戦で先制点を挙げた南野拓実。練習からギラつく20歳前後の若手たちに囲まれながら、30歳になった自分の立ち位置を静かに受け止めている。日本代表に呼ばれて10年。かつて自分も“勢いだけの若者”だった時代がある。その記憶を抱えながら、今はキャプテンマークを巻き、彼らの背中を押す側へ――。森保ジャパンが世代交代を迎える渦
2025.11.18 16:45 Tue
 ガーナ戦のピッチに立った鹿島アントラーズの守護神・早川友基。正GK鈴木彩艶の負傷、第2GK大迫敬介の不在の中で巡ってきたチャンスを、無失点という最高の形で終えた。だが、試合後のミックスゾーンに現れた早川の表情に、満足の色はなかった。代表2戦目にして、“守るだけ”のGKでは終わらない次のステージを見据えていた。
■
2025.11.18 15:30 Tue
ガーナ戦のピッチに立った鹿島アントラーズの守護神・早川友基。正GK鈴木彩艶の負傷、第2GK大迫敬介の不在の中で巡ってきたチャンスを、無失点という最高の形で終えた。だが、試合後のミックスゾーンに現れた早川の表情に、満足の色はなかった。代表2戦目にして、“守るだけ”のGKでは終わらない次のステージを見据えていた。
■
2025.11.18 15:30 Tue
記事をさがす
|
|
原口元気の人気記事ランキング

1
日本代表の背番号11/六川亨の日本サッカー見聞録
アジアカップはカタール代表の初優勝で終わり、5度目の戴冠を期待された日本代表は残念ながら準優勝に終わった。準決勝のイラン代表戦では今大会でベストのパフォーマンスから3-0の快勝を収めただけに、後手に回った決勝戦での前半の戦いぶりが悔やまれる。 そのカタール戦、ハーフタイムに控えの選手がピッチでボールを蹴っていたが、乾貴士と遠藤航の姿がなかった。0-2とリードされていただけに、「後半から乾と遠藤の2枚替えか。遠藤がボランチに戻れば守備を立て直すことができるが、体調は大丈夫なのか?」と期待したものの、森保一監督は動かなかった。 最初の交代カードは後半16分、原口元気に代えて武藤嘉紀を起用した。すると19分と21分に武藤が立て続けにヘッドでゴールを狙ったものの、シュートはクロスバーを越え、同点のチャンスを逃してしまった。決めていれば2011年カタール大会決勝の李忠成のようなヒーローになれただけに、武藤にとっては悔いの残るシュートだっただろう。 ただ、最初の交代カードで武藤を抜擢したが、彼の武器であるスピードはスペースがあってこと生きるタイプだ。カタールは自陣のゴール前を固めてカウンター狙いだったため、ゴールをこじ開けるにはクロスに対しガムシャラに飛び込む北川航也の方が効果的ではなかったかと疑問が残る。 それまで5試合に起用し、サブ組のFWでは最長の出場時間だっただけに、なぜ最後までベンチに温存したのか。北川が森保監督の期待に応えることができなかったと言われればそれまでだし、結果論にすぎないという反論もあることは百も承知だ。 そして改めて思うのは、北川は運がないということ。それは北川だけに限らず、今回彼が背負った日本代表の「背番号11」はなぜか結果に恵まれないということだ。 北川の前に「背番号11」を背負っていた選手が誰かと聞かれても、即答できるファンは数少ないのではないだろうか。ロシアW杯での「背番号11」は宇佐美貴史だったが、ほとんど活躍できなかった。 その前は豊田陽平であり、その前はというと柿谷曜一朗、原口元気、ハーフナー・マイク、前田遼一、玉田圭司、播戸竜二、佐藤寿人、巻誠一郎、鈴木隆行、黒部光昭、松井大輔、鈴木隆行、中山雅史、三浦淳寛、呂比須ワグナー、小野伸二、三浦知良らが「背番号11」を背負ってきた。 彼らの中で記憶に残るゴールを決めた選手となると、2002年日韓W杯の初戦ベルギー代表戦(2-2)で同点ゴールを決め、W杯で初めて勝点1をもたらした鈴木くらいではないだろうか。あとは“キング・カズ”の存在感が圧倒的だった。 もともと「背番号11」は左ウイングに与えられるナンバーだったものの、ポジションが流動化した現代サッカーでは9番と10番と同様に攻撃的な選手、ストライカーに与えられる番号でもある。にもかかわらず、日本代表の歴代「11番」は、カズ以降ストライカーとしての輝きを放てていない。 果たして3月に再招集される森保ジャパンにおいて、誰が「背番号11」を受け継ぐのか。そしてゴールという結果を出すことができるのか。23人のメンバーとともに注目したいと思っている。 2019.02.05 16:45 Tue
2
日本代表の“11番”と言えば?新たな“キング”は生まれるか
11月11日は「ポッキー&プリッツの日」として有名だが、サッカーが11人同士で戦うことから、「サッカーの日」としても知られている。 そこで今回は日本代表の「11」番にフォーカス。近年の日本代表で背負った選手たちを紹介したい。 背番号「11」はもともと左ウイングのポジションに与えられていた番号で、現代サッカーにおいても攻撃的な選手が着用していることが多い。横浜FCの元日本代表FW三浦知良も「11」を長年着用している。 <div id="cws_ad">◆今から31年前、コリチーバ時代の三浦知良のプレー集<br/><div style="margin:0 auto; max-width:100%; min-width:300px; " ><div style="position: relative; padding-bottom:56.25%; height: 0; overflow: hidden; "><iframe src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJ6dmY0SERPaSIsInAiOiJ1bHRyYXNvY2NlciIsInBsIjoiIn0=" style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top:0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden; " width="100%" frameborder="0" allowfullscreen scrolling="no"></iframe></div></div></div> “キング・カズ”は日本代表でも背番号「11」を着用。日本の「11」番と言えば真っ先に名前が挙がる選手だ。 カズの次に「11」番を着用したのは小野伸二だ。小野は1998年に行われたフランス・ワールドカップ(W杯)でもこの番号を背負っていた。まさかのメンバー外となったカズの番号を当時18歳の小野が背負うことは当時大きな話題となった。 その後は呂比須ワグナー、三浦淳寛、中山雅史、鈴木隆行が背負い、2002年の日韓W杯では鈴木が日本代表の背番号「11」を背負った。 それからは松井大輔、黒部光昭、一度鈴木隆行に戻った後に巻誠一郎が着用。2006年のドイツW杯では巻が日本の「11」番だった。 「11」番の入れ替わりは激しく、佐藤寿人、播戸竜二、玉田圭司、前田遼一、ハーフナー・マイク、原口元気、柿谷曜一朗、豊田陽平といったフォワードたちが背負ってきたが、中々日本代表での結果には恵まれていない。 直近のロシアW杯での宇佐美貴史や、2019年のアジアカップで「11」番を背負った北川航也らも、ゴールという結果を出せなかった一人だ。 今年10月の国際親善試合では、堂安律がこれまでの「21」番ではなく「11」番を背負ったものの、11月のオーストリア遠征ではクラブ事情により代表不参加が決定している。 今後、堂安が背番号「11」を自らの番号とする活躍を見せるのか。それとも別の“キング”が誕生することになるのか。日本代表の「11」番に注目していきたい。 <div style="text-align:left;" id="cws_ad">◆“キング・カズ”以降の日本代表「11」番<br />三浦知良:~1997-98<br />小野伸二:1997/98<br />呂比須ワグナー:1998/99-99/00<br />三浦淳寛:1999/2000<br />中山雅史:2000/01<br />鈴木隆行:2001/02-04/05<br />松井大輔:2002/03<br />黒部光昭:2003/04<br />巻誠一郎:2005/06<br />佐藤寿人:2007/08<br />播戸竜二:2007/08-09/10<br />玉田圭司:2008/09-10/11<br />宮市亮:2011/12<br />清武弘嗣:2011/12<br />藤本淳吾:2011/12<br />前田遼一:2011/12<br />ハーフナー・マイク:2011/12-13/14<br />原口元気:2013/14<br />柿谷曜一朗:2014/15<br />豊田陽平:2014/15<br />宇佐美貴史:2014/15-17/18<br />齋藤学:2016/17<br />久保裕也:2017/18<br />乾貴士:2017/18<br />小林悠:2017/18<br />北川航也:2018/19<br />三好康児:2019/20<br />永井謙佑:2019/20<br />田川亨介:2019/20<br />堂安律:2020/21</div> 2020.11.11 19:05 Wed
3
“お祭り男”槙野智章の引退試合は夫婦揃ってPK弾! 後半からは本田圭佑監督が異様な存在感で指揮…槙野氏は最後にレッドカードでSNS上喝采「最高の引退試合じゃん(笑)」
14日、元日本代表DF槙野智章の引退試合「槙野智章 大感謝祭〜1日限りのワッショイ劇場〜」がノエビアスタジアム神戸で行われており、試合終盤には槙野氏の奥さま、俳優の高梨臨さんも登場して会場を盛り上げた。 サンフレッチェ広島、ケルン、浦和レッズ、ヴィッセル神戸に所属し、日本代表としては通算38キャップおよび2018年W杯出場の槙野氏。 引退から約2年、神奈川県社会人サッカー1部リーグの品川CCで監督を務めるなか、古巣神戸の本拠地ノエビアで引退試合が開催された。 今回は本田圭佑が監督を務める「MAKINO JAPAN」と吉田孝行監督(ヴィッセル神戸)率いる「KOBE STARS」の対戦となり、槙野氏は「MAKINO JAPAN」としてフル出場。 「MAKINO JAPAN」は試合前に「参加したいと言ったことは一度もない」と話した本田監督がスタメン出場。そのほか、吉田麻也、香川真司、原口元気、宇賀神友弥、森脇良太などが先発に名を連ねる。 現役の神戸選手を中心とした「KOBE STARS」では、この試合に合わせて来日したルーカス・ポドルスキ(グールニク・ザブジェ/ポーランド1部)がキャプテンとして先発出場。 槙野氏は“盟友”ポドルスキにも容赦なくスライディングタックルを仕掛け、守備対応後にノエビアのスタンドを煽ってブーイングを浴びる一幕も。詰めかけたファンを沸かせていく。 「MAKINO JAPAN」は22分、本田のシュートでハンドを誘発してPK獲得。キッカー槙野はGK飯倉大樹の手をかすめた強烈な右足シュートを突き刺し、引退試合で自ら先制点とする。 後半は本田がスーツ&サングラスでビシッとキメてピッチ脇から指揮。1点を追う「KOBE STARS」には後半から大迫勇也、武藤嘉紀、酒井高徳が加わり、徐々に攻勢をかける。 存在感が突き抜けた“本田圭佑監督”にSNS上も盛り上がるなか、ポドルスキが至近距離のFKを直接狙う場面も。強烈な左足の一撃は、1度目は壁に入った那須大亮が頭でCKに逃げ、2度目はGK飯倉が横っ飛びのセーブで弾き出す。 そんななか「MAKINO JAPAN」に追加点。槙野氏のフィードから、最後は今季で現役を引退する興梠慎三がこぼれ球に詰めてネットを揺らした。本田監督も拍手で称える。 前半にPKで先制点の槙野氏だが、今度はPKを献上。それでも“盟友”GK西川周作が小林祐希のシュートを阻止し、本田監督も大喜び。 試合終盤には再びPKを獲得した「MAKINO JAPAN」。すると、槙野氏の奥さま、高梨臨さんが現れ、急遽途中出場。 背番号10の高梨さんは、GK前川にシュートをキャッチされるも、村上主審は蹴り直しを命じ、バニシングスプレーで至近距離にボールをセット。高梨さんは2度目のキックで成功し、「MAKINO JAPAN」に3点目がもたらされた。 直後、ゴールセレブレーションでコーナーフラッグを引き抜いた槙野氏にイエローカード。さらにその後、なぜか?VARが発動し、村上主審が会場にマイクで説明…槙野氏は引退試合でレッドカードを提示されることとなった。 試合後には槙野氏自ら出場選手に表彰を与えるなどしており、大感謝祭らしく最後まで全開。SNS上も「最高の引退試合じゃん(笑)」「本田監督うつるたびにわろてまう(笑)」等々盛り上がり、笑顔の絶えない引退試合となっている。 MAKINO JAPAN 3-0 KOBE STARS 【MAKINO】 槙野智章(前24)※30分ハーフ 興梠慎三(後20) 高梨臨(後30) <span class="paragraph-title">【動画】高梨臨さんがPK成功</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">[速報] <a href="https://twitter.com/hashtag/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E8%87%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#高梨臨</a> さん が出場し得点!<br><br>/<br>槙野夫妻が同じピッチに立ち、<br>まさかの高梨臨さんがPKを決める!!<br>\<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%E6%A7%99%E9%87%8E%E6%99%BA%E7%AB%A0%E5%A4%A7%E6%84%9F%E8%AC%9D%E7%A5%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#槙野智章大感謝祭</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/ABEMA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ABEMA</a> で【無料】生中継<a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%A2%E3%83%99%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%A5%AD%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#アベマサッカー祭り</a></p>— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) <a href="https://twitter.com/ABEMA_soccer/status/1867852796114219055?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.12.14 17:46 Sat
4
日本代表スタメン発表!長谷部誠が復帰、井手口陽介、浅野拓磨、乾貴士が先発!《ロシアW杯アジア最終予選》
▽31日に行われるロシア・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。 ▽勝てば6大会連続6度目のワールドカップ出場が決定する日本。オーストラリア代表との大一番に、キャプテンのMF長谷部誠(フランクフルト)が復帰した。その他、FW原口元気(ヘルタ・ベルリン)やFW本田圭佑(パチューカ)、MF香川真司(ドルトムント)らが外れ、FW乾貴士(エイバル)、FW浅野拓磨(シュツットガルト)、MF井手口陽介(ガンバ大阪)が先発に名を連ねた。 ▽また、昨日発表されていた23名にも変更があり、MF高萩洋次郎(FC東京)、FW杉本健勇(セレッソ大阪)が外れ、DF三浦弦太(ガンバ大阪)、MF小林祐希(ヘーレンフェーン)がベンチ入りしている。 ▽オーストラリアとの大一番は、31日の19時35分から埼玉スタジアム2002で行われる。 <div style="text-align:center;"><img src="http://image.ultra-soccer.jp/800/image/get20170831_15_tw2.jpg" style="max-width: 100%;"></div><div style="text-align:right;font-size:x-small;">(C)CWS Brains,LTD.<hr></div>【スタメン】 GK:川島永嗣 DF:酒井宏樹、吉田麻也、昌子源、長友佑都 MF:山口蛍、長谷部誠、井手口陽介 FW:浅野拓磨、大迫勇也、乾貴士 【サブ】 GK:東口順昭、中村航輔 DF:酒井高徳、三浦弦太、槙野智章 MF:本田圭佑、香川真司、小林祐希、柴崎岳 FW:原口元気、岡崎慎司、久保裕也 2017.08.31 18:19 Thu
5
ハメスはベンチスタート、対コロンビア戦の日本代表スタメン《ロシアW杯》
▽本日19日21時にキックオフを迎えるロシア・ワールドカップ(W杯)グループH第1節のコロンビア代表vs日本代表(@モルドヴィア・アリーナ/サランスク)のスターティングメンバ―が発表された。 ▽6大会連続6回目のW杯出場となる日本代表。本大会開幕前に突然の監督交代で激震が走ったが、過去最高位ベスト16超えの挑戦がいよいよ幕を開ける。西野朗監督は、本番前最後となる調整試合のパラグアイ代表戦から先発を6名変更した。 ▽守護神をGK川島永嗣が務め、最終ラインにDF酒井宏樹、DF吉田麻也、DF昌子源、DF長友佑都。ボランチにMF長谷部誠とMF柴崎岳を置き、1トップを務めるFW大迫勇也の背後にMF原口元気、MF香川真司、MF乾貴士を起用した。 ▽なお、対戦相手のコロンビア代表は、ケガを抱えるMFハメス・ロドリゲスがベンチスタート。主砲のFWラダメル・ファルカオがスターティングメンバー入りを果たした。 ◆vsコロンビアの日本代表スタメン<div style="text-align:center;"><img src="http://ultra-soccer.jp/division_image/TOP/get20180619_28_tw2.jpg" style="max-width: 100%;"></div><div style="text-align:right;font-size:x-small;">(C)CWS Brains,LTD.<hr></div>GK:川島永嗣 DF:酒井宏樹、吉田麻也、昌子源、長友佑都 MF:長谷部誠、柴崎岳、原口元気、香川真司、乾貴士 FW:大迫勇也 2018.06.19 20:15 Tue日本の人気記事ランキング

1
「なんて可愛いんでしょ」オナイウ阿道が妻と愛娘と家族ショット、七五三での着物姿に「とってもかわいい」など祝福の声
トゥールーズに所属するFWオナイウ阿道の愛娘が愛くるしい。 2021年6月にキリンチャレンジカップ2021のセルビア代表戦で日本代表デビューを果たしたオナイウ。同年夏に海を渡り、活躍の場を横浜F・マリノスからフランスに移している。 28日には自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開した。 家族4人での幸せフォトや、着物姿でカメラに目を向ける長女の姿には、ファンからも祝福の声や感嘆の声が届いている。 「素敵なご家族、お似合いです」 「なんて可愛いんでしょ、おめでとうございます」 「七五三おめでとうございます。ますます素敵な女の子になられますように」 「ちっちゃい女の子たちがとってもかわいい」 オナイウは2018年に入籍を発表。2人は2019年7月10日に第一子となる長女を、2020年9月26日に第2子となる次女を授かっていた。 <span class="paragraph-title">【写真】オナイウ阿道の愛娘の着物姿</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Cmr-DTzqt7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cmr-DTzqt7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Cmr-DTzqt7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">オナイウ阿道 2022.12.29 20:35 Thu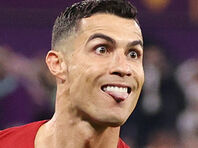
2
21世紀の出場試合数ランキング発表! 首位は1145試合のC・ロナウド、トップ10に日本人選手がランクイン
IFFHS(国際サッカー歴史統計連盟)が、21世紀で最もプレーした選手のランキングを発表。トップ10には日本人選手もランクインした。 様々な統計を行うIFFHS。2022年までのデータを集計し、21世紀に入ってからのプレーした試合数をもとにランキングを作成した。 対象となるのは、各国のリーグ戦やカップ戦、国際カップ戦、代表チームの試合も含まれ、全ての公式戦が対象になっている。 今回の統計では1000試合以上プレーした選手が3人に増加。首位は昨年と変わらず、サウジアラビアへ活躍の場を移したポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)となり、1145試合を記録した。 2022年に1000試合を突破したのは、ブラジル代表DFダニエウ・アウベス(UNAMプーマス)とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(パリ・サンジェルマン)。アウベスは1033試合、メッシは1003試合となった。メッシはカタール・ワールドカップ(W杯)での試合で1000試合を超えたことになる。 そんな中、8位には日本人がランクイン。941試合に出場したMF遠藤保仁(ジュビロ磐田)だ。遠藤はガンバ大阪と磐田、そして日本代表での試合が21世紀に含まれている。なお、アジア人でも唯一となり、900試合以上を達成しているのも12名となっている。 ◆21世紀の出場試合数ランキング 合計(国内リーグ/国内カップ/国際カップ/代表) 1位:クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) 1145試合(651/93/205/196) 2位:ダニエウ・アウベス(ブラジル) 1033試合(620/115/172/126) 3位:リオネル・メッシ(アルゼンチン) 1003試合(559/102/170/172) 4位:イケル・カシージャス(スペイン) 974試合(585/57/171/161) 5位:ジョアン・モウティーニョ(ポルトガル) 958試合(563/107/142/146) 6位:ズラタン・イブラヒモビッチ(スウェーデン) 948試合(603/72/152/121) 7位:ルカ・モドリッチ(クロアチア) 947試合(569/69/146/162) 8位:遠藤保仁(日本) 941試合(606/117/66/152) 9位:チャビ・エルナンデス(スペイン) 937試合(536/95/174/132) 10位:セルヒオ・ラモス(スペイン) 935試合(534/70/151/180) 11位:アンドレス・イニエスタ(スペイン) 933試合(552/98/152/131) 12位:ロジェリオ・セニ(ブラジル) 904試合(675/71/149/9) 2023.01.12 12:45 Thu
3
「何度見ても鳥肌」ブラジルW杯出場を掴んだ本田圭佑の豪州戦“ど真ん中PK”にファン大興奮「やっぱメンタル強すぎ」
7大会連続7度目のワールドカップ(W杯)出場を懸けて、最終予選のラスト2試合を戦う日本代表。24日には出場を争うオーストラリア代表との大一番を控えている。 そんな中、日本サッカー協会(JFA)の公式SNSが2014年のブラジルW杯出場を決めたオーストラリア戦でのMF本田圭佑のPKに再び焦点を当てている。 当時、アルベルト・ザッケローニ監督のもとで5大会連続のW杯出場を目指した日本は、MF本田圭佑、MF香川真司、FW岡崎慎司ら海外組を主軸に、最終予選で4勝1分けと好発進。早くも予選突破に王手をかけると、ヨルダンとのアウェイゲームに敗れるという波乱もあったものの、オーストラリアとのホームゲームに臨む。 試合終盤の82分に失点を許す厳しい展開となったが、後半アディショナルタイムにPKを獲得。そのキッカーを本田が務めた。 ゴールマウスにはオーストラリアの守護神マーク・シュウォーツァー。緊張感の漂うなか、本田は大きく息を吐いてから助走をスタート。左足のPKをど真ん中に蹴り込むと、埼玉スタジアム2002のスタンドからは轟音のような歓声が鳴り響いた。 試合はこのまま1-1の引き分けとなり、日本は開催国ブラジルを除いて最速でのW杯本大会出場を決めていた。 このタイミングで本田のPKシーンをJFAが公開したところ、多くのファンが反応。「最高でした」、「やっぱこのPKを蹴れるってメンタル強すぎだな」、「この瞬間は一生忘れないと思う」、「何度見ても鳥肌立つ 何度見ても感動する」といったコメントが寄せられており、多くの人の記憶に刻まれているようだ。 日本はこのブラジル大会だけでなく、2018年のロシア大会のアジア最終予選でもオーストラリア戦でW杯出場の切符を手にしている。24日の試合で勝利すればその時点でカタールへの切符を手にすることとなるが、この大一番を制することはできるだろうか <span class="paragraph-title">【動画】何度でも見られる! 本田圭佑がど真ん中に決めたW杯出場を決めるPK</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CbYjGz1BVNn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">日本サッカー協会(JFA)/日本代表/なでしこジャパン(@japanfootballassociation)がシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> 2022.03.22 20:30 Tue
4
「素晴らしいムービーありがとう」W杯の熱量そのままに!開幕へ向けたJリーグのPVが大反響「四年後じゃない。二ヶ月後だ」
ワールドカップ(W杯)の熱気を冷ましてしまうのはもったいない。 日本代表の活躍も記憶に新しいカタールW杯はアルゼンチン代表の優勝で閉幕したが、サッカーファンにはとっては高校サッカー、インカレ、皇后杯など、まだまだイベントが続く。 23日には来季のJリーグ開幕節の日程も発表に。さらにJリーグは翌日、公式SNSで開幕へ向けたプロモーションビデオを公開した。 各W杯戦士がJリーグチームに在籍していた際の懐かしいユニフォームをファンが着用し、試合を注視。さらに当時の映像に加え、ラストにはサプライズも盛り込まれてる。 「Jリーグから巣立った選手たちが、カタールで戦っていた。」 「祭りが終わって、もうすぐ日常が始まる。」 「次の主役たちは、たぶん、私たちの日常の中にいる。もしかしたら、いつものスタジアムのピッチに。」 「また、ここから始めよう。」 「四年後じゃない。二ヶ月後だ。」 「2023年2月17日、Jリーグ開幕。」 近年では新卒で海外挑戦をする選手や海外クラブの育成組織へ加入するプレーヤーも増加しているが、カタールW杯を戦った日本代表26選手は全員がJリーグ経験者。中にはJ3でのプレー経験を持つ選手もいる。 過去から未来へとつながる映像には、ファンからも「素晴らしいムービーありがとうございます」、「感動したわ」、「泣かせますやん」、「2ヶ月後とか待ちきれないな」などの声が届けられたほか、現役選手やOBからも大きな反響が寄せられている。 <span class="paragraph-title">【動画】Jリーグ開幕へ向けた煽りPV</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="A32xw6cPO3w";var video_start = 0;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2022.12.24 15:50 Sat
5

























