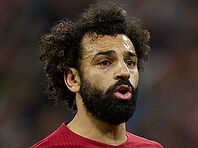アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島
2025.09.30 16:50 Tue
アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島
2025.09.30 16:50 Tue
過去にもあった相手スローインを奪っての得点/六川亨の日本サッカー見聞録
2022.10.14 22:20 Fri

J1リーグは横浜Mの優勝が濃厚かと思われたものの、雲行きが怪しくなってきた。2位の川崎Fの結果次第だったとはいえ、優勝に“王手"をかけながらホームで残留争いの渦中にあるG大阪(17位)と磐田(18位)にまさかの連敗。対照的に川崎Fは苦しみながらも清水と京都に連勝した結果、一時は8あった勝点差は2まで縮まった。残りは2試合で、両チームとも5連勝でJ1残留を決めた神戸戦を残しているところが興味深い。ただ、追いかける川崎FはGKチョン・ソンリョンが札幌戦で右膝内側の側副靱帯を損傷。CBジェジエウも札幌戦で右第5中手骨頚部を骨折して手術を受けたため、2人ともラスト2試合を欠場せざるを得ない。守備の中心選手を欠くだけに、川崎Fにとっては試練の2試合と言えよう。
一方、残留争いも佳境を迎え、22日には18位の磐田(勝点28)が17位の清水(同32)とアイスタで激突する。当日はルヴァンカップの決勝も開催されるが、注目度では静岡ダービーの方が“熱い"かもしれない。
そんな今シーズンのJ1リーグで、記憶に残るのは第28節の福岡対名古屋戦での同点ゴールではないだろうか。
簡単に試合を振り返ると、福岡のMFクルークスが接触プレーで倒れたため、名古屋のMFレオ・シルバがボールをタッチラインの外へ蹴り出した。当然、福岡のスローインで試合は再開となるが、福岡の選手は名古屋にボールを返すのが「暗黙のルール」であり、福岡DF前嶋は名古屋GKランゲラックにボールを戻した。
試合は当然ながら名古屋のキックオフで再開された。ところが福岡の長谷部監督は選手らにプレーに関わらないように指示を出す。「故意による失点」で1点を返そうとしたわけだ。こうしたプレーに主審は関与できない。そして名古屋FW永井がゆっくりとしたドリブルで持ち込み2-1となる逆転弾を決めた。
こうしたプレーは今回が初めてのケースではない。過去には03年3月8日のナビスコカップ(現ルヴァンカップ)グループリーグ初戦の京都対大分戦で同様のことがあった。
大分FW高松大樹が負傷したため京都MFの松井大輔がタッチライン外にボールを出した。大分DF若松大樹のスローインを受けたMF寺川能人は京都GKにボールを返したが、このボールを大分MFロドリゴがさらってドリブルで突進すると、そのまま大分の勝ち越しゴール(2-1)を決めてしまった。
突然の出来事に選手はもちろん観客も驚いたが、大分の小林伸二監督は冷静だった。京都のキックオフによるプレー再開に際し、大分の選手たちに「プレーを止める」よう指示。すると京都MF中払大介がペナルティーエリアの外から蹴り込んで2-2の同点に追いついた(試合は3-2で京都の勝利)。
ロドリゴはボールを奪うと躊躇うことなく京都ゴールに突進してゴールを決めたわけだが、「ゴールはゴール、自分が決めたかった」とシーズン開幕での得点にこだわった。
福岡のルキアンも、大分のロドリゴも悪気があったわけではないだろうし、“暗黙の了解"を知らなかったわけでもないだろう。実際、彼らのプレーは反則ではないため、レフェリーも笛を吹くことはなかった。
そして19年ぶりの「故意の失点」で思い出したのが、04年のアテネ五輪アジア最終予選でのプレーだった。ゴールにはならなかったため正式な記録として残っていないが、UAEで開催された第1ラウンドで日本はマイボールのスローインを相手チームに返した。当然、相手は日本ボールに返すと思ったところ、ボールを受けた選手はハーフライン付近から日本ゴールに向かってドリブル突破を始めた。
慌てた日本はゴールまで距離があったため、ドリブル突破を阻止することができた。そして試合後、当該選手は最近になって国籍を取得したアフリカ出身の選手で、スローインのボールを相手チームに返すという行為そのものを知らなかったためのアクシデントだったとの説明があった。
しかしチームを率いる山本昌邦監督は、「相手がスローインを返さないことも想定してプレーしなければならない」と選手に警鐘を鳴らした。
ボールを返さずにゴールを決めたとしても反則ではない。そして生まれた1点が試合の結果を左右し、国際大会での予選突破につながったとしても、公式記録に残るのは最終スコアとゴールを決めた選手の名前だけである。例えそれが道義的にアンフェアなプレーによる得点だったとしても、そのことが記録されることはない。
W杯や五輪などの最終予選では、日本が不利益を被っても相手チームが「故意の失点」で日本にゴールを“お返し"してくれるとは限らないだろう。ここらあたりが国際試合と国内リーグとの違いかもしれない。
話を福岡対名古屋戦に戻すと、試合開始早々に相馬のロングパスをクリアしようとして自陣に戻る福岡DF宮と、ペナルティーエリアを飛び出したGK永石が空中で激突。頭と頭がぶつかる危険なプレーだった。
しかし中村主審は味方同士の突発的な接触であり、クリアボールは福岡陣内の左サイドにこぼれ、それを名古屋の選手が追いかけたため笛を吹くことはなかった。そしてこのプレーから最後はポストの跳ね返りを森下が決めて名古屋が先制点を奪った。
直後に中村主審は笛を吹いて名古屋のゴールを認めつつ、担架を呼んだが、GK永石は脳しんとうの疑いがあるため交代を余儀なくされた。危険なプレーがあったにもかかわらず、主審は笛を吹かずに名古屋のゴールを認めた。このプレーが伏線にあるため、「ルキアンは仕返しじゃないけど、自分たちだって同じではないかという思いが出てしまったのかもしれない」と長谷部監督はかばった。
しかし続けて「でもそれは違う。それを選手たちにも理解してもらい、過ちを修正した」と名古屋のキックオフに守備の放棄を指示して名古屋に1点を贈った。
もしも中村主審が福岡の選手同士の激突に笛を吹いていたら、名古屋の先制点は生まれなかったかもしれないし、ルキアンの強奪によるゴールもなかったかもしれない。少なくとも後味の悪い試合にはならなかっただろう。
一方、残留争いも佳境を迎え、22日には18位の磐田(勝点28)が17位の清水(同32)とアイスタで激突する。当日はルヴァンカップの決勝も開催されるが、注目度では静岡ダービーの方が“熱い"かもしれない。
簡単に試合を振り返ると、福岡のMFクルークスが接触プレーで倒れたため、名古屋のMFレオ・シルバがボールをタッチラインの外へ蹴り出した。当然、福岡のスローインで試合は再開となるが、福岡の選手は名古屋にボールを返すのが「暗黙のルール」であり、福岡DF前嶋は名古屋GKランゲラックにボールを戻した。
ところがここで問題が発生した。福岡FWルキアンがこのボールを奪うとゴール前へクロス。これに先ほどまで倒れていたクルークスが反応して左足で押し込んでしまったのだ。
試合は当然ながら名古屋のキックオフで再開された。ところが福岡の長谷部監督は選手らにプレーに関わらないように指示を出す。「故意による失点」で1点を返そうとしたわけだ。こうしたプレーに主審は関与できない。そして名古屋FW永井がゆっくりとしたドリブルで持ち込み2-1となる逆転弾を決めた。
こうしたプレーは今回が初めてのケースではない。過去には03年3月8日のナビスコカップ(現ルヴァンカップ)グループリーグ初戦の京都対大分戦で同様のことがあった。
大分FW高松大樹が負傷したため京都MFの松井大輔がタッチライン外にボールを出した。大分DF若松大樹のスローインを受けたMF寺川能人は京都GKにボールを返したが、このボールを大分MFロドリゴがさらってドリブルで突進すると、そのまま大分の勝ち越しゴール(2-1)を決めてしまった。
突然の出来事に選手はもちろん観客も驚いたが、大分の小林伸二監督は冷静だった。京都のキックオフによるプレー再開に際し、大分の選手たちに「プレーを止める」よう指示。すると京都MF中払大介がペナルティーエリアの外から蹴り込んで2-2の同点に追いついた(試合は3-2で京都の勝利)。
ロドリゴはボールを奪うと躊躇うことなく京都ゴールに突進してゴールを決めたわけだが、「ゴールはゴール、自分が決めたかった」とシーズン開幕での得点にこだわった。
福岡のルキアンも、大分のロドリゴも悪気があったわけではないだろうし、“暗黙の了解"を知らなかったわけでもないだろう。実際、彼らのプレーは反則ではないため、レフェリーも笛を吹くことはなかった。
そして19年ぶりの「故意の失点」で思い出したのが、04年のアテネ五輪アジア最終予選でのプレーだった。ゴールにはならなかったため正式な記録として残っていないが、UAEで開催された第1ラウンドで日本はマイボールのスローインを相手チームに返した。当然、相手は日本ボールに返すと思ったところ、ボールを受けた選手はハーフライン付近から日本ゴールに向かってドリブル突破を始めた。
慌てた日本はゴールまで距離があったため、ドリブル突破を阻止することができた。そして試合後、当該選手は最近になって国籍を取得したアフリカ出身の選手で、スローインのボールを相手チームに返すという行為そのものを知らなかったためのアクシデントだったとの説明があった。
しかしチームを率いる山本昌邦監督は、「相手がスローインを返さないことも想定してプレーしなければならない」と選手に警鐘を鳴らした。
ボールを返さずにゴールを決めたとしても反則ではない。そして生まれた1点が試合の結果を左右し、国際大会での予選突破につながったとしても、公式記録に残るのは最終スコアとゴールを決めた選手の名前だけである。例えそれが道義的にアンフェアなプレーによる得点だったとしても、そのことが記録されることはない。
W杯や五輪などの最終予選では、日本が不利益を被っても相手チームが「故意の失点」で日本にゴールを“お返し"してくれるとは限らないだろう。ここらあたりが国際試合と国内リーグとの違いかもしれない。
話を福岡対名古屋戦に戻すと、試合開始早々に相馬のロングパスをクリアしようとして自陣に戻る福岡DF宮と、ペナルティーエリアを飛び出したGK永石が空中で激突。頭と頭がぶつかる危険なプレーだった。
しかし中村主審は味方同士の突発的な接触であり、クリアボールは福岡陣内の左サイドにこぼれ、それを名古屋の選手が追いかけたため笛を吹くことはなかった。そしてこのプレーから最後はポストの跳ね返りを森下が決めて名古屋が先制点を奪った。
直後に中村主審は笛を吹いて名古屋のゴールを認めつつ、担架を呼んだが、GK永石は脳しんとうの疑いがあるため交代を余儀なくされた。危険なプレーがあったにもかかわらず、主審は笛を吹かずに名古屋のゴールを認めた。このプレーが伏線にあるため、「ルキアンは仕返しじゃないけど、自分たちだって同じではないかという思いが出てしまったのかもしれない」と長谷部監督はかばった。
しかし続けて「でもそれは違う。それを選手たちにも理解してもらい、過ちを修正した」と名古屋のキックオフに守備の放棄を指示して名古屋に1点を贈った。
もしも中村主審が福岡の選手同士の激突に笛を吹いていたら、名古屋の先制点は生まれなかったかもしれないし、ルキアンの強奪によるゴールもなかったかもしれない。少なくとも後味の悪い試合にはならなかっただろう。
アビスパ福岡の関連記事
 アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島
2025.09.30 16:50 Tue
アビスパ福岡の秘密兵器がJリーグデビュー戦で初ゴールをあげた。陸上選手であるサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟であるFWサニブラウン・ハナンのゴールにファンたちが歓喜した。
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!ゴール (91:44)ハナン サニブラウンアビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島
2025.09.30 16:50 Tue
 17日、明治安田J1リーグ第17節でアビスパ福岡と名古屋グランパスがベスト電器スタジアムで対戦した。
一時は首位に立つも6戦未勝利で12位まで転落した福岡。3連敗中と苦しい流れの中、前節からは4名を変更。永石拓海、橋本悠、見木友哉、シャハブ・ザヘディが外れ、村上昌謙、田代雅也、前嶋洋太、紺野和也が入った。
2025.05.17 16:35 Sat
17日、明治安田J1リーグ第17節でアビスパ福岡と名古屋グランパスがベスト電器スタジアムで対戦した。
一時は首位に立つも6戦未勝利で12位まで転落した福岡。3連敗中と苦しい流れの中、前節からは4名を変更。永石拓海、橋本悠、見木友哉、シャハブ・ザヘディが外れ、村上昌謙、田代雅也、前嶋洋太、紺野和也が入った。
2025.05.17 16:35 Sat
 Jリーグは14日、5月15日の「Jリーグの日」を記念し、開幕当時に多くのファンに親しまれた「Jリーグチップス」を特別に復刻することを発表した。
1993年の開幕とともに人気を博した「Jリーグチップス(選手カード付)」が、32周年を迎えるJリーグに帰ってくることに。復刻版では、J1、J2、J3の全60クラブから各3
2025.05.14 15:55 Wed
Jリーグは14日、5月15日の「Jリーグの日」を記念し、開幕当時に多くのファンに親しまれた「Jリーグチップス」を特別に復刻することを発表した。
1993年の開幕とともに人気を博した「Jリーグチップス(選手カード付)」が、32周年を迎えるJリーグに帰ってくることに。復刻版では、J1、J2、J3の全60クラブから各3
2025.05.14 15:55 Wed
 10日、11日にかけて明治安田J1リーグ第16節の10試合が全国各地で行われた。
【京都vs名古屋】終盤にスコアが動いた中ドロー
連敗で首位から陥落も劇的勝利で3位に位置している京都サンガF.C.と降格圏からなんとか抜け出した17位の名古屋グランパスの対戦となった。
上位と下位の対決となった試合。名古
2025.05.11 19:25 Sun
10日、11日にかけて明治安田J1リーグ第16節の10試合が全国各地で行われた。
【京都vs名古屋】終盤にスコアが動いた中ドロー
連敗で首位から陥落も劇的勝利で3位に位置している京都サンガF.C.と降格圏からなんとか抜け出した17位の名古屋グランパスの対戦となった。
上位と下位の対決となった試合。名古
2025.05.11 19:25 Sun
 10日、明治安田J1リーグ第16節の横浜FCvsアビスパ福岡がニッパツ三ツ沢球技場で行われ、ホームの横浜FCが1-0で勝利した。
前節、東京ヴェルディに0-2で敗れて今季初の3連敗となった19位の横浜FC。6戦ぶりの白星を目指した中3日でのホームゲームでは先発4人を変更。福森晃斗、鈴木準弥、鈴木武蔵、ルキアンがベ
2025.05.10 16:03 Sat
10日、明治安田J1リーグ第16節の横浜FCvsアビスパ福岡がニッパツ三ツ沢球技場で行われ、ホームの横浜FCが1-0で勝利した。
前節、東京ヴェルディに0-2で敗れて今季初の3連敗となった19位の横浜FC。6戦ぶりの白星を目指した中3日でのホームゲームでは先発4人を変更。福森晃斗、鈴木準弥、鈴木武蔵、ルキアンがベ
2025.05.10 16:03 Sat
J1の関連記事
 【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2-0 柏レイソル(2月21日/メルカリスタジアム)
2月21日、22日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節の中で飛び出したスーパープレーを伝える『超ワールドサッカー的今節のサブイボプレー』。今節は鹿島アントラーズのGK早川友基が見せ
2026.02.23 20:36 Mon
【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2-0 柏レイソル(2月21日/メルカリスタジアム)
2月21日、22日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節の中で飛び出したスーパープレーを伝える『超ワールドサッカー的今節のサブイボプレー』。今節は鹿島アントラーズのGK早川友基が見せ
2026.02.23 20:36 Mon
 【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1-1(PK:5ー4)ファジアーノ岡山(2月14日/エディオンピースウイング広島)
スペシャル岡山のマエストロ江坂任 右足一閃、振り抜いた明治安田J1百年構想リーグ広島×岡山DAZN 無料LIVE配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.co
2026.02.16 19:36 Mon
【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1-1(PK:5ー4)ファジアーノ岡山(2月14日/エディオンピースウイング広島)
スペシャル岡山のマエストロ江坂任 右足一閃、振り抜いた明治安田J1百年構想リーグ広島×岡山DAZN 無料LIVE配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.co
2026.02.16 19:36 Mon
 ファジアーノ岡山がキャンプ地の宮崎でセレッソ大阪とのトレーニングマッチを翌日に控えた1月23日、練習を終えたFWウェリック・ポポは取材ゾーンの前に“寄り道”をしていた。向かった先にいたのは、就任5年目を迎える木山隆之監督だ。
190cm86kgのブラジル人ストライカーは、親指を立てながら指揮官に宣言した。
2026.01.29 12:00 Thu
ファジアーノ岡山がキャンプ地の宮崎でセレッソ大阪とのトレーニングマッチを翌日に控えた1月23日、練習を終えたFWウェリック・ポポは取材ゾーンの前に“寄り道”をしていた。向かった先にいたのは、就任5年目を迎える木山隆之監督だ。
190cm86kgのブラジル人ストライカーは、親指を立てながら指揮官に宣言した。
2026.01.29 12:00 Thu
 ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を
2025.12.30 20:00 Tue
ファジアーノ岡山は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で清水エスパルスと対戦し、1-2で勝利を収めた。11試合ぶりの勝利に沸くピッチで、岡山のDF工藤孝太は真っ先にDF立田悠悟のもとへ向かった。J1の壁にぶつかり続けた若きDFと、自らの過去を重ねて支え続けた先輩。2026シーズンも共闘が決まった、2人の熱き師弟関係を
2025.12.30 20:00 Tue
 12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡
2025.12.23 19:30 Tue
12月17日、横浜FCの山根永遠がファジアーノ岡山に加入することが発表された。J1昇格の歓喜も、残留争いの苦しみも知る彼の移籍リリースには、横浜FCサポーターからたくさんの「ありがとう」をはじめ別れを惜しむ声が集まった。そして、岡山のサポーターは活躍を期待している。山根永遠とは、どんな選手なのか。編集部に所属しながら岡
2025.12.23 19:30 Tue
|
|
アビスパ福岡の人気記事ランキング

1
福岡がDF柳貴博と契約解除、信号待ちの居眠りで酒気帯び運転発覚…札幌から来季は完全移籍予定
アビスパ福岡は29日、北海道コンサドーレ札幌より期限付き移籍中のDF柳貴博(25)に関して、期限付き移籍契約解除を発表した。 クラブの発表によると、柳は27日に酒気帯び運転を行い、道路交通補違反で任意捜査されたとのこと。28日付で、契約を解除したという。 柳は27日の午前9時頃に発覚。26日の深夜から自宅で飲酒。27日の朝に、アルコール成分が体内に残ったまま、8時頃に自家用車でクラブハウスへ向かったという。 その際、交差点にて信号待ちで居眠り。駆け付けた警察官の呼気検査にて基準値を超えるアルコールが検知されたとのことだ。 代表取締役社長の川森敬史氏は、クラブを通じてコメントしている。 「この度の不祥事により、弊クラブにご支援をいただいておりますスポンサー、ファン、サポーターの皆様をはじめ、関わる全ての皆様へご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」 「酒気帯び運転は、極めて危険な行為であり断じて許されない行為です。今回の事態を重く受け止め、選手・スタッフ、クラブ在籍者を対象に、管内の警察に協力を仰ぎ「交通安全講習会」を実施のうえ、コンプライアンス教育を再度徹底し、継続的な再発防止策に取り組んでまいります」 また、保有元の札幌も今回の事象について報告。完全移籍する予定だったが、その話も無くなったとした。 「弊クラブとアビスパ福岡、及び柳選手とは、2022年3月からの期限付き移籍、2023年2月からの完全移籍について合意しており、現所属クラブであるアビスパ福岡様の意思決定である選手契約解除を、北海道コンサドーレ札幌としても尊重いたします」 「飲酒・酒気帯び運転は決して許されるものではありません。Jリーグに関わる方々、ファン、サポーターの皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。社会の規範であるべきプロサッカー選手、そしてJリーグクラブとして、再発防止も含めまして選手、スタッフ、社員への教育を再徹底し、改めて、コンプライアンス遵守に関する意識を高めてまいります」 柳は今季の明治安田生命J1リーグで13試合、YBCルヴァンカップで4試合に出場していた。 2022.08.29 21:33 Mon
2
Jリーグが理念強化配分金とファン指標配分金の支給額を発表! 「DAZN」ベースのファン指標分配金の1位は浦和、最下位はYSCCに…連覇神戸は5.5億円
Jリーグは25日、2025年度理念強化配分金の支給対象候補クラブ、2024年度ファン指標配分金支給対象クラブを発表した。 理念強化配分金は、2023年の明治安田生命J1リーグで1位から10位に対して送られるもの。20チーム制に変更となったために1チーム増えることとなった。また、2024シーズン年間ファン指標順位(DAZN視聴者数等1~10位)に基づいても支給される。 競技面では連覇を達成したヴィッセル神戸から10位のセレッソ大阪までに支給され、神戸は2025年、2024年にそれぞれ2億5000万円ずつを手にする。なお、2023年も優勝したため、その分の2億5000万も今回支給される。また、2位のサンフレッチェ広島には2年間で1億8000万円ずつ、3位のFC町田ゼルビアは、1億5000万円(2025年)と7000万円(2026年)を手にする。なお、2023年2位の横浜F・マリノスには1億8000万円、3位の広島には7000万円がしキュされる。 また、ファン指標順位は1位は2024年も浦和レッズとなり1億7000万円。2位が鹿島アントラーズで1億2000万円、3位が横浜FMで7000万円と続き、10位は名古屋グランパスで1000万円となった。なお、競技順位で10位以内に入っていないクラブでは、1位の浦和、10位の名古屋に加え、8位に北海道コンサドーレ札幌が入り2000万円となった。 さらに、「ファン指標配分金」として、13億6000万円をJリーグの全60クラブに分配。これは、2024シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分され、1位が浦和で8921万5930円。2位が横浜FMで7945万2984円、3位が川崎フロンターレで6648万1993円となっている。なお、最下位はY.S.C.C.横浜となり182万4625円が分配される。 <h3>◆理念強化配分金(競技)/総額11億2000万円</h3> 1位:ヴィッセル神戸 1年目ー2億5000万円、2年目ー2億5000万円 2位:サンフレッチェ広島 1年目ー1億8000万円、2年目ー1億8000万円 3位:FC町田ゼルビア 1年目ー1億5000万円、2年目ー7000万円 4位:ガンバ大阪 1年目ー1億5000万円、2年目ーなし 5位:鹿島アントラーズ 1年目ー1億2000万円、2年目ーなし 6位:東京ヴェルディ 1年目ー9000万円、2年目ーなし 7位:FC東京 1年目ー6000万円、2年目ーなし 8位:川崎フロンターレ 1年目ー5000万円、2年目ーなし 9位:横浜F・マリノス 1年目ー4000万円、2年目ーなし 10位:セレッソ大阪 1年目ー3000万円、2年目ーなし <h3>◆理念強化配分金(人気)</h3> 1位:浦和レッズ/1億7000万円 2位:鹿島アントラーズ/1億2000万円 3位:横浜F・マリノス/7000万円 4位:ヴィッセル神戸/5000万円 5位:川崎フロンターレ/4000万円 6位:サンフレッチェ広島/3000万円 7位:ガンバ大阪/2000万円 8位:北海道コンサドーレ札幌/2000万円 9位:FC町田ゼルビア/1000万円 10位:名古屋グランパス/1000万円 <h3>◆ファン指標配分金</h3>(昨年との金額比較) 1位:浦和レッズ/8921万5930円(↑) 2位:横浜F・マリノス/7945万2984円(↑) 3位:川崎フロンターレ/6648万1993円(↓) 4位:鹿島アントラーズ/6598万4095円(↓) 5位:ヴィッセル神戸/6491万8131円(↑) 6位:ガンバ大阪/5864万8883円(↑) 7位:名古屋グランパス/5851万4812円(↓) 8位:北海道コンサドーレ札幌/5315万3249円(↑) 9位:FC東京/4924万9886円(↑) 10位:サンフレッチェ広島/4572万5356円(↑) 11位:FC町田ゼルビア/4558万3908円(↑) 12位:アルビレックス新潟/4466万3143円(↓) 13位:ジュビロ磐田/4426万2918円(↑) 14位:セレッソ大阪/3988万8434円(↓) 15位:サガン鳥栖/3834万3648円(↑) 16位:柏レイソル/3695万3904円(↓) 17位:湘南ベルマーレ/3554万5920円(↓) 18位:東京ヴェルディ/3459万9966円(↑) 19位:京都サンガF.C./3438万1632円(↑) 20位:清水エスパルス/3362万962円(↓) 21位:アビスパ福岡/3259万3587円(↓) 22位:ベガルタ仙台/2298万6246円(↑) 23位:V・ファーレン長崎/1758万2571円(↑) 24位:大分トリニータ/1716万3388円(↑) 25位:ファジアーノ岡山/1704万1315円(↑) 26位:横浜FC/1664万9981円(↓) 27位:ジェフユナイテッド千葉/1608万1426円(↓) 28位:モンテディオ山形/1442万3396円(↓) 29位:ヴァンフォーレ甲府/1362万8966円(↓) 30位:松本山雅FC/1324万9873円(↑) 31位:ロアッソ熊本/1008万4227円(↓) 32位:栃木SC/983万8888円(↓) 33位:徳島ヴォルティス/934万7583円(↓) 34位:RB大宮アルディージャ/925万5971円(↓) 35位:ザスパ群馬/888万8344円(↓) 36位:レノファ山口FC/886万2864円(↓) 37位:いわきFC/878万641円(↓) 38位:鹿児島ユナイテッドFC/825万2572円(↑) 39位:愛媛FC/768万2897円(↑) 40位:水戸ホーリーホック/718万9579円(↓) 41位:藤枝MYFC/708万1435円(↓) 42位:ツエーゲン金沢/622万6288円(↓) 43位:ブラウブリッツ秋田/619万6520円(↓) 44位:カターレ富山/481万4398円(↑) 45位:ギラヴァンツ北九州/459万264円(↓) 46位:FC岐阜/396万9504円(↓) 47位:SC相模原/341万1253円(↓) 48位:FC今治/327万7554円(↓) 49位:AC長野パルセイロ/317万8338円(↓) 50位:カマタマーレ讃岐/313万7389円(↓) 51位:FC琉球/309万4569円(↓) 52位:福島ユナイテッドFC/288万7440円(↑) 53位:ガイナーレ鳥取/282万3403円(↓) 54位:ヴァンラーレ八戸/265万6822円(↓) 55位:いわてグルージャ盛岡/261万6733円(↓) 56位:アスルクラロ沼津/251万5766円(↓) 57位:テゲバジャーロ宮崎/237万4594円(↑) 58位:FC大阪/226万1536円(↑) 59位:奈良クラブ/223万1534円(↓) 60位:Y.S.C.C.横浜/182万4625円(↓) 2025.02.25 17:40 Tue
3
J昇格請負人だったウーゴ・マラドーナの訃報/六川亨の日本サッカー見聞録
昨年末のこと、残念なニュースが飛び込んできた。一昨年末に亡くなったディエゴ・マラドーナの末弟であるウーゴ・マラドーナ(52歳)が急逝したとの報道だ。死因はナポリにある自宅で心臓発作を起こしたらしい。 ディエゴ自身もこれまで放映された映画やアマゾンTVが放送しているドラマなどで、ナポリ時代に薬物に手を出したことを告白している。もしかしたらウーゴも同じ道を辿ったとしたら、兄ディエゴは“英雄"だったかもしれないが、ファミリーにとってナポリ時代は悔やまれてならない。 ウーゴの存在を身近に知ったのは、92年に浜松市をホームにするPJMフューチャーズに加入した時だった。 PJMは、アメリカ人のポール・J・マイヤーが開発した人材育成のための能力開発システムで、当時、本田技研の研修を担当していた桑原勝義氏が興味を持ったことから“おとぎ話"はスタートした。桑原は藤枝東高時代に高校選手権で優勝し、その後は日本代表にも選ばれた好選手で、本田サッカー部の監督も歴任した(現JFL理事長)。 桑原氏の夢は、一貫した育成システムで育てた選手を2002年のW杯で日本代表に送り込むことだった。そのために本田を辞め、87年にクワバラスポーツクラブと、本田サッカー部の選手を中心にしたPJMフューチャーズを立ち上げた。 当初の予定は7年後の94年にJSL(日本サッカーリーグ)1部入りを果たすことだったが、時代はJリーグ創設へと動き出した。 Jリーグ入りへ、静岡からはJSL1部のヤマハと本田に加え、県リーグ所属の清水クラブ(後の清水エスパルス)の4チームが名乗りを上げた(その後は中央防犯、現アビスパ福岡もJリーグ入りを表明)。後発であり劣勢が否めないPJMにとって、Jリーグ入りへ起死回生の策だったのが当時29歳のディエゴ・マラドーナの獲得だった。 90年7月、PJMフューチャーズのオーナーでありPJMジャパンの社長の有田平は「移籍金は20億円以上、年俸も希望次第」と発表した。しかしナポリとの契約が93年5月まで残っていたため、マラドーナの獲得は夢のまま終わった。 そんなPJMフューチャーズに転機が訪れたのは東海リーグに昇格した91年、マラドーナ3兄弟の末弟であるウーゴを獲得したことだった。兄に似てずんぐりむっくりの体型のウーゴは、「背番号10は兄ディエゴのためにとっておく」と話していた。ディエゴの夢である「兄弟3人(ラウルとウーゴ)でプレーする」ための布石ではないかと報道されることもあった。 残念ながら兄ディエゴは90年イタリアW杯後の91年にコカイン服用の疑いでイタリア警察から告発され、FIFAからは15ヶ月の出場停止処分を受け、兄弟が揃って日本でプレーする夢はかなわなかった。 それでもウーゴはPJM(後の鳥栖フューチャーズ)でプレーした92年から94年の3年間(東海リーグとJFL)で49試合出場31ゴール、95年は福岡ブルックスに移籍し、JFLでは27試合出場で27ゴールを奪ってJリーグ昇格に貢献、97年には札幌でもチームをJリーグ昇格へと導いた。 偉大すぎる兄と比較されながらも、そのひたむきなプレーは鳥栖や福岡、札幌のファン・サポーターの脳裏に焼き付いているのではないだろうか。遅ればせながら、哀悼の意を表します。 2022.01.10 12:30 Mon
4
「相手選手へのリスペクトに欠けるものでした」福岡・クルークスが物議醸したフェアプレー無視のゴールを謝罪
アビスパ福岡のMFジョルディ・クルークスが、物議を醸したゴールを謝罪した。 3日、明治安田生命J1リーグ第28節のアビスパ福岡vs名古屋グランパスは波乱続出の展開となった。 試合は開始2分になる手前、ロングボールを処理しようとした福岡のGK永石拓海がボックスを飛び出ると、バックステップでクリアしようとしたDF宮大樹と頭同士が激突。そのまま2人とも倒れ込むが、味方同士の接触でもあり、この流れでプレーは止まらず、名古屋が森下龍矢のゴールで先制する。 早々にアクシデントが起こり、異様な雰囲気が漂う中、20分に再びアクシデントが起きる。 20分に福岡のクルークスがタックルを受けるが、これは正当なチャージに。しかし、痛んで倒れていたため、名古屋のレオ・シルバがボールを外に蹴り出した。 クルークスは大事に至らずプレーは再開。福岡の前嶋洋太がスローインで名古屋のGKランゲラックに戻そうとしたところ、このボールを福岡のルキアンがカット。クロスを上げると、クルークスが蹴り込み、同点に追いついていた。 このプレー自体はルールに違反したわけではないが、通例では相手選手が試合を止めるために故意に外に蹴り出したため、相手にボールを返すのがフェアプレー。どの試合でも見られる行為だが、それを無視してゴールを決めてしまった。 当然名古屋側が激怒。紳士協定違反と見られ、怒りを露わにするのは当然。そして、怒りの収まらない名古屋は、長谷川健太監督が長谷部茂利監督のところへ。2人の話し合いの結果、福岡が無抵抗で1点を与えることとなり、キックオフから永井謙佑が1人で持ち込んでゴールを決めた。 このゴールを決めてしまったクルークスは、一夜明けて自身のインスタグラムのストーリーズで謝罪した。 「みなさん、こんにちは」 「まずは、昨日のゴールについて皆さんに謝りたいです。あのゴールは、相手選手へのリスペクトに欠けるものでした」 「ただ、あのプレーは故意的なものではありませんでした」 「いつも僕を応援してくださっている方なら、僕がフェアで、誰に対してもリスペクトを欠かさない選手であると知ってくれているはずです」 「僕は最後までアビスパ福岡のために闘います。一緒に乗り越えましょう」 試合中は興奮状態にもあり、パスが来たから反射的にシュート打った可能性は考えられる。大きな物議を醸しただけに、冷静な判断をしてもらいたいところだ。 <span class="paragraph-title">【動画】物議醸した福岡のプレーから監督の話し合い、無抵抗のゴール献上までの一部始終をノーカットで</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="HDti8D63Gx8";var video_start = 0;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2022.09.04 21:05 Sun
5