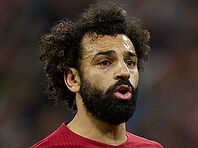50mを6秒後半で走る小学6年生の井関流季也 エコノメソッドで育むスピードの賢い使い方|U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2025
2025.08.25 12:30 Mon

他の人よりも足が速い。その能力を小学生で手にした者は、無双状態だ。新学年が始まってから間もなくして行われる体力テストでクラスで1番のタイムを出せば、クラスメイトからの憧れの視線を浴びる。運動会でリレーのアンカーを務めれば、友だちからの期待を一手に集める。誰もが羨む能力である。
小学生年代のサッカーにおいても、速さというのは圧倒的な武器だ。スペースに突いたボールを相手よりも先に追いつくことができれば、それだけで突破できてしまう。そのまま1人でゴールを決めることもできる。シンプルではあるが、ピッチ内で他を圧倒できる特殊能力だと言っていい。
だが、それは時には諸刃の剣となってしまう。スピードだけに依存して技術や判断を疎かにしていると、周りが身体的な成長によって自分のスピードに追いついてきたら、今までのように活躍することは難しくなってしまう。
だが、エコノメソッド選抜の一員としてU-12ワールドチャレンジ(以下、ワーチャレ)に出場したFW井関流季也くんは違った。小学6年生ながら50mを6秒後半で走る俊足を持ちながら、スピードに依存していない。惜しくも敗れてしまったが、準決勝・malva fc戦は緩急の使い分けが非常にスムーズだった。18分に相手ゴール前でボールを奪ってネットを揺らした後、特にハーフタイムを迎えるまでの約7分間は左サイドの主導権を完全に握っていた。相手との1対1で前方にスペースがあれば、大きく持ち出して縦に突破する。相手との1対2で数的不利であれば、マークを引きつけて裏に走る味方にスルーパスを出す。状況を的確に判断し、効果的にスピードを発揮していた。
そのスピードの有効活用こそ、エコノメソッドスクールで学んでいることだという。
普段から練習を見ている小林裕人コーチも、スクールに通い始めてから約半年での成長ぶりに太鼓判を押す。
「溜季也は、スピードが速くて身体能力に優れた選手ですが、そのスピードを生かしたドリブルを使うタイミングをよく理解できています。最初の頃はボールを持てば足元のうまさで突破できちゃう選手だったので、ボールだけを見てプレーしていた印象でしたが、たった半年でボールを持っていない時に周りを見ることができるようになっていて、ワールドチャレンジ準決勝のようなトップレベルの大会でも活躍できる選手に成長してくれたと思います」
スピードによる突破力という武器を持っているが、それをむやみに振りかざすことはしない。相手を抜くことは目的ではなく、ゴールを決めて、チームを勝利に導くための手段だから。
井関くんはベスト4に終わった今大会を経て、「GKとの1対1までは行けるけど、そこで抜き切るのか、ゴールに対して身体の向きをつくってシュートを決めるのか。そこが苦手だから、決めるように意識していきたいです」と、自分の突破をゴール数に結びつけることに注力していくつもりだ。
これまで数々のスポーツに取り組んできたが、中学受験を機に、5歳から始めたサッカーに1本化した。テニスや水泳だけでなく、関東3位に輝いたこともある卓球をやめたのも、親御さんとの相談のもとで「サッカーが自分の1番生きる場所だと思ったから。スピードとか、自分の運動神経と合っているのがサッカーだった」と自分の特徴を把握した結果のようだ。
突出する身体能力に技術をプラスし、エコノメソッドで学ぶ賢さを完全習得した時、三笘薫のような日本を代表するドリブラーへの道が切り拓かれるのかもしれない。
取材・文=難波拓未
小学生年代のサッカーにおいても、速さというのは圧倒的な武器だ。スペースに突いたボールを相手よりも先に追いつくことができれば、それだけで突破できてしまう。そのまま1人でゴールを決めることもできる。シンプルではあるが、ピッチ内で他を圧倒できる特殊能力だと言っていい。
だが、それは時には諸刃の剣となってしまう。スピードだけに依存して技術や判断を疎かにしていると、周りが身体的な成長によって自分のスピードに追いついてきたら、今までのように活躍することは難しくなってしまう。
そのスピードの有効活用こそ、エコノメソッドスクールで学んでいることだという。
「自分はドリブル重視だったから、スペースや相手の位置など周りを見て、ドリブルとパスの使い分けを学ぶために通うようになりました」
普段から練習を見ている小林裕人コーチも、スクールに通い始めてから約半年での成長ぶりに太鼓判を押す。
「溜季也は、スピードが速くて身体能力に優れた選手ですが、そのスピードを生かしたドリブルを使うタイミングをよく理解できています。最初の頃はボールを持てば足元のうまさで突破できちゃう選手だったので、ボールだけを見てプレーしていた印象でしたが、たった半年でボールを持っていない時に周りを見ることができるようになっていて、ワールドチャレンジ準決勝のようなトップレベルの大会でも活躍できる選手に成長してくれたと思います」
スピードによる突破力という武器を持っているが、それをむやみに振りかざすことはしない。相手を抜くことは目的ではなく、ゴールを決めて、チームを勝利に導くための手段だから。
井関くんはベスト4に終わった今大会を経て、「GKとの1対1までは行けるけど、そこで抜き切るのか、ゴールに対して身体の向きをつくってシュートを決めるのか。そこが苦手だから、決めるように意識していきたいです」と、自分の突破をゴール数に結びつけることに注力していくつもりだ。
これまで数々のスポーツに取り組んできたが、中学受験を機に、5歳から始めたサッカーに1本化した。テニスや水泳だけでなく、関東3位に輝いたこともある卓球をやめたのも、親御さんとの相談のもとで「サッカーが自分の1番生きる場所だと思ったから。スピードとか、自分の運動神経と合っているのがサッカーだった」と自分の特徴を把握した結果のようだ。
突出する身体能力に技術をプラスし、エコノメソッドで学ぶ賢さを完全習得した時、三笘薫のような日本を代表するドリブラーへの道が切り拓かれるのかもしれない。
取材・文=難波拓未
|
|